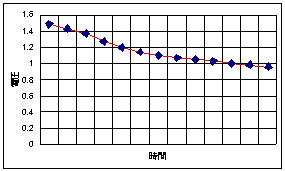|
1 研究に取り組んだ観察,実験 単元名 エネルギー 「化学変化で電気エネルギーを取り出してみよう」 実験名 「燃料電池に関する実験」 東京書籍「新しい科学1下(P84)」
2 観察,実験のねらい 教科書では,燃料電池の学習に関して,簡易電気分解装置を用いて電子オルゴールを鳴らす方法が記述してあるが,この方法だと電子オルゴールの鳴る時間が短すぎるという問題点があった。そこで,さらにパワーのある燃料電池を自作し,いろいろな実験をしてみようと考え,本研究を行った。
3 観察,実験の実際と問題点 まず,簡易電解装置を用いて燃料電池の実験を行った。 ① 02%NaOH水溶液500mlを準備。 ② 10Vの電圧を1分間与え,電気分解を行った。 ③ 電気分解後,電極にテスターをつなぎ,内部抵抗による電圧降下の様子を15秒ごとに測定した。
-時間経過による電圧降下の様子- -左の表をグラフにしたもの-
※LEDの動作範囲→ 3.0~6.0V,25mA ※太陽電池用モーターの動作範囲→ 0.4~1.5V,22~40mA
問題点 この簡易電解装置による燃料電池の実験では,LEDは点灯せず,太陽電池用モーターも回らなかった。その原因として,①起電力が1.2Vしか出ないこと。②内部抵抗が大きく,電流が長時間流れないことが考えられる。 したがって,燃料電池の実験を行う場合,この簡易電解装置を用いるのは適切でないと思われる。 4 観察実験の改善のポイント,開発した教材道具 上記の実験結果より,簡易電解装置に代わるものがないかと考えた時,ペットボトルを用いて燃料電池の実験を行う方法があることを知り,さっそく実験を行った。(市販の500mlペットボトルを使用)
○ペットボトル燃料電池の作成 ① 鉛筆をガスコンロで燃やす。しばらくすると,木の部分が炭化してボロボロになるので,芯の部分だけを取り出す。(加熱し過ぎると,芯が折れる場合があるので注意する。)
② 芯(炭素棒)の表面をサンドペーパーで軽くこする。表面に細かい傷をつけることで,表面積を大きくし,気体が吸着しやすい電極となる。
③ ペットボトルのキャップに3箇所の穴を開ける。2箇所は電極用1箇所は発生ガスのガス抜き用である。(穴を開ける時は,熱した釘を押しつける方法で簡単に穴が開く)
④ キャップの穴に2本の電極を通す。電極が穴から抜け落ちないように,接着剤で固定する。電極の先端部分の間隔が狭まるようにすると,より多くの電流を取り出せるようになる。
⑤ ペットボトル燃料電池の試運転(2%食塩水で実施)
太陽電池用モーター LEDが点灯した! が回った!
○ペットボトル燃料電池の性能評価
1.濃度の違いについて 電解質の濃度が高くなれば起電力も高くなり,モーター作動時間が長くなるのではないかと考え,NaOH水溶液の濃度を変えて実験を行った。 (通電時間→1分,電極の間隔→3mm,電極の水没深度→8cm) <測定結果>
< 考察 > 起電力にはそれほど差は見られなかったが,濃度が高くなるとモーターの作動時間が長くなることが分った。生徒実験時の安全性を考えた場合,電解質の濃度は2%程度に抑えていた方がよいと思われる。
2.電気分解時の通電時間による違いについて 電気分解により,大量のH2とO2を発生させれば,多くの電流を取り出すことができるのではないかと考え,通電時間を変化させて実験を行った。 (NaOH濃度→2%,電極の間隔→3mm,電極の水没深度→8cm) <測定結果>
<考察> 起電力にそれほど差は見られなかったが,通電時間が長くなるとモーターの作動時間が長くなることが分った。通電時間が長くなれば,それだけ電極表面にH2とO2の気泡が付着するためだと思われる。
3.電極の間隔について 2つの電極の間隔が小さければ,多くの電流を取り出せるのではないかと考え,電極の間隔を変化させて測定を行った。 (NaOH濃度→2%,通電時間→1分,電極の水没深度→8cm) <測定結果>
< 考察 > 起電力にそれほど差は見られなかったが,電極の間隔が小さい方がモーターの作動時間が長くなることが分った。これは,陰極で発生したH+が陽極に移動して水になる反応がしやすくなるためだと考える。
4.液面下に水没する電極の長さ(水没深度)について 電極が液面下に水没する部分が長くなれば,水溶液と接する表面積が大きくなり,多くの電流を取り出せるのではないかと考え,電極の水没深度を変えて測定を行った。 (NaOH濃度→2%,通電時間→1分,電極の間隔→3mm) <測定結果>
< 考察 > 起電力にはそれほど差は見られなかったが,電極の水没深度が大きい方がモーターの作動時間が長くなることが分った。これは,水溶液と接する電極の表面積が大きくなり,H2とO2の気泡をたくさん付着させることができるためだと考える。
5.電解質の種類について 電解質の種類による起電力,内部抵抗の違いを見るために,電解質なし, NaCl,NaOHの3種類について,実験を行った。 (通電時間→1分,電極の間隔→3mm,電極の水没深度→8cm) <測定結果>
< 考察 > 電解質にNaClを使用すると,起電力も高く,モーター作動時間も長くなることが分った。しかしこの場合,電気分解時に有害なCl2が陽極から発生し,安全性に問題が出てくる。したがって,電解質にはHaOHを使用するのがよいと考える。
○本研究の結論 本研究の実験結果から,ペットボトル燃料電池は生徒実験用の装置として,経済性,安全性,そして実験成功率の面からも有効であると考える。 その際,①安全性を考えると,2%のNaOH水溶液でも十分である。 ②電気分解の際の通電時間は1分程度でよい。 ③2本の電極の間隔を狭め,水没する部分の長さを長くする。 ④NaClは電気分解時にCl2が発生するので使用しない。 等に留意することで,ペットボトル燃料電池の能力を十分に発揮できるものと考える。
○参考文献 ・滝川洋二・吉村利明著「ガリレオ工房の身近な道具で大実験・第3集」 (大月書店) ・本間琢也監修「燃料電池のしくみがわかる本」(技術評論社) ・秋田県秋田市岩美三内中学校 エコルーム部門燃料電池製作班のHP「自作燃料電池の研究」 ・兵庫県川西市立多田中学校 前田誠通先生のHP「課題研究の指導(理科)」 ・仲井真梨,石田聡一,千川圭吾,信州大学教育学部実践報告「燃料電池システム教材の開発と授業実践」
重富中学校 南木純一 |