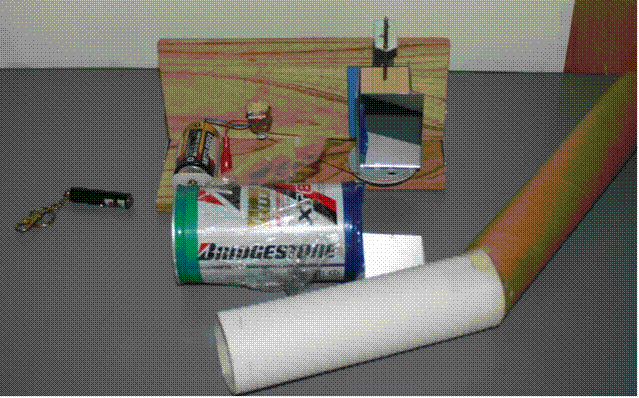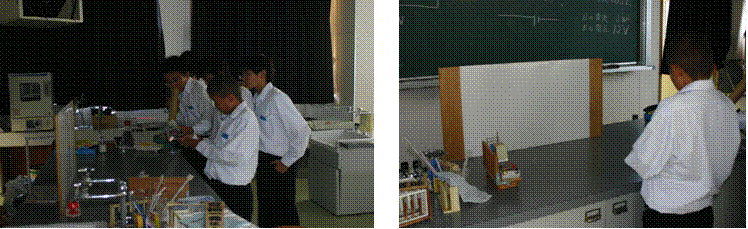|
1 研究に取り組んだ観察,実験 1分野上 実験3音の大小や高低と物体の振動との関係を調べよう 2 観察,実験のねらい 音の大小や高低は,発音体の振動の振幅と振動数に関係することをとらえさせる。 3 観察,実験の実際と問題点 (1) モノーコードやギターなどの弦を1本はじいて音の大きい・小さい,高い・低いをだし弦の振動の様子を観察する。 (2) 弦の振動は観察しにくい。 4 観察,実験のポイント,開発した教材教具 (1) 観察実験のポイント ア 発音体に人の声を用い,正弦波が観察できるようにする。 イ 人の声の振動を,鏡とレーザー光を使って可視化する。 ウ 波の頂点がずれて観察できるように,一定周期で回転する四面鏡を用いる。
(2) 開発した教材教具 ア 材料 ① 回転鏡…真ちゅうの棒,アクリルミラー4枚(発泡ポリスチレンの大きさ),発泡ポリスチレン ② マイク…筒(φ8cm程度),ラップフィルム,ビニルテープ,アクリルミラー(3㎝×2㎝) ③ 本体…パネル(厚さ1㎝,縦35㎝×横10㎝)モーター,乾電池ボックス,銅線,100W電熱線(20cm),L字型金具,木ねじ,プーリー,輪ゴム,木ネジ,真ちゅう釘 ④ その他…レーザー光源,輪転機マスターなどの芯 イ 製作過程 (ア) 回転鏡 ① 発泡ポリスチレンを4cm角に切り抜き,その中心に真ちゅう棒を通す穴を開ける。 ② アクリルミラーを発泡ポリスチレンに貼り付ける。 ③ 真ちゅう棒にプーリーを取り付け,発泡ポリスチレンの穴に通す。 (イ) マイク ① 筒の底をぬく。 ② 筒の一方の口にたるみが生じないようにラップフィルムを貼り付ける。 ③ アクリルミラー(3㎝程度×2㎝程度)を,筒の縁から1/3程度はみだすようにして,両面テープでラップフィルムに貼り付ける。 (ウ) 本体 ① 取り付け位置を決め,L字型金具と乾電池ボックスを木ねじで,モーターを銅線で取り付ける。 ② 乾電池ボックスとモーター,電熱線などをはんだ付けする。 ③ 本体を組み立て,回転鏡を取り付ける。 5 実証実験の流れと結果及び考察 第2学年の教科担任であるため,第1学年の復習として,教師実験として実施した。生徒の方に実験を説明して,生徒と一緒に実験をする。生徒達は,自分の声が波長として写るので高い音・低い音,大きい音・小さい音と実験を楽しんでいた。
6 実証授業の成果と課題 自分の声が波長として現れるので生徒は進んで,実験に取り組んでくれた。ただ,一個しかないので,教師実験になった。班の個数来年は作りたい。 アクリルミラー4枚を発泡ポリスチレンにうまく張らないとレーザー光の線が一定にならない。 コンピュータの波形表示ソフトと一緒に使うことで,より効果が上がると考えられる。 日置市立伊集院北中学校 福 和人 |