|
1 研究に取り組んだ観察,実験 磁界を立体的に観察できるようにする教材教具 2 観察,実験のねらい 本単元のねらいは,静電気や電流回路の実験を通して,電流と電圧との関係及び電流のはたらきについて理解するとともに,日常生活と関連付けて電流と磁界について初歩的な見方や考え方を養い,電流に対する興味・関心を高めることである。学習指導要領でも電流のはたらきに関して「磁石や電流による磁界の観察を行い,磁界を磁力線で表すことを理解するとともに,コイルの回りに磁界ができることを知ること」と述べられている。 3 観察・実験の実際と問題点
4 観察,実験の改善のポイント,開発した教材教具 棒磁石で最も磁力が強いのは両端の磁極の部分である。片方をN極,もう一方をS極といい,磁石には必ずこの二つの極がある。2本の棒磁石の磁極を近づけると,同極どうしでは反発しあい,異なる極を近づけると引き合う。このとき,磁極間にはたらいている力を磁力といい,磁石の磁力が及んでいる空間を磁界(磁場)と呼ぶ。磁力線はこの磁界を表現するもので,見ることはできないが,紙の上に広げた砂鉄に裏側から磁石を近づけると,模様ができて平面的に磁力線をイメージすることができる。これは, (1)砂鉄入りカードケース(右図) 【材料】 ① カードケース(B5サイズ) ② 砂鉄 【製作方法】 カードケースに適量の砂鉄を入れる。
【材料】 ① 炭酸飲料用500mlペットボトル ② アクリルパイプ(外径1.7cm) ③ ゴム栓(4号) ④ サラダ油450ml ⑤ スチールウール 【製作方法】 ① アクリルパイプを長さ20cmに切り,その先にゴム栓をきつく閉めこむ(写真1)。 ② ペットボトルのキャップに錐で穴を開け,その周囲を彫刻刀で削ってアクリルパイプが通る大きさの穴にする。パイプを通して隙間を接着剤でしっかりとシールする(写真2)。 ③ スチールウールをできるだけ細かく切る(写真3)。
⑥ 2で加工したパイプをペットボトルの中に入れ,キャップをしっかりと閉め,接着剤でシールする。 5 実証授業の流れと結果および考察 (1) 学習過程
(2) 結果及び考察 ア 砂鉄入りカードケース これまでの授業では,砂鉄を直接磁石につけることから扱いが難しく,生徒もなかなか実験に集中することができなかった。こ 【磁石をおいた場合】【同極(N極)同士を向かい合わせた場合】 イ 磁界提示装置 アや教科書の提示だけでは,磁界への理解を平面的なものに終わらせてしまいがちだが,この提示装置を使用することで立体的な磁界を表現することができた。生徒の反応も上々で,感嘆の声を上げていた。制作費も1個当たり約300円と安価で,生徒にも製作できるほど簡単な装置である(これらの装置は3年選択の生徒が製作した)。ただ,今後の課題としてはキャップの部分のシールが不十分で振ると油が漏れてきてしまう点,磁石を入れる際,勢いあまってゴム栓が外れてしまう点を改良していかなければならない。 【管に磁石を入れたときのようす】【外からN極同士を向かい合わせたときの様子】 6 実証授業の成果と課題 今回の授業では,磁石による磁界のようすを効果的に提示できる教材の開発,改善に取り組み,電流による磁界の学習が円滑に進められるような授業構成を考えた。研究の成果としては, ○ 開発教材を用いることで,実験がスムーズに行え,探究活動に集中させることができた。 ○ 生徒の興味・関心を高めさせることができた。 ○ 磁石による磁界への理解を平面ではなく,立体的にとらえさせることができた。 などが挙げられる。 課題としては,5 実証授業の流れと結果および考察の(2)でも述べたが, ○ カードケースの砂鉄が全体的に均一に散らばることは案外難しく,全体的にきれいな磁力線を描かせることはできなかった。 ○ キャップの部分のシールが不十分で振ると油が漏れることがある。 ○ 磁石を入れる際,勢いあまってゴム栓が外れてしまう。 などが挙げられる。 また,当初は電流による磁界の提示装置の開発を目指したが,パスカル電線を使い,電源装置を4個直列でつなぎ40Vの電圧を加えてやっと同心円状の模様ができた程度であった。これらを理科室で実用化するには,放熱等の危険が伴い教具として開発することはできなかった。今後継続して取り組んでいきたい。 鹿児島市立郡山中学校 久德 晋也 |
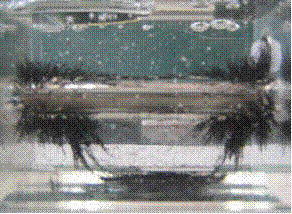
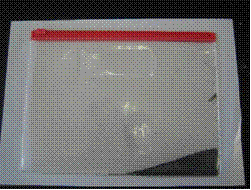 砂鉄が磁化されて磁石になり,異なる極どうしがつながったためだが,
砂鉄が磁化されて磁石になり,異なる極どうしがつながったためだが, (
(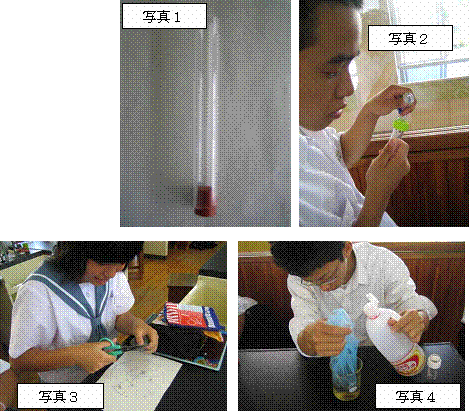 ④ 細かく切ったスチールウールを混ぜたサラダ油をペットボトルに入れる(写真4)。
④ 細かく切ったスチールウールを混ぜたサラダ油をペットボトルに入れる(写真4)。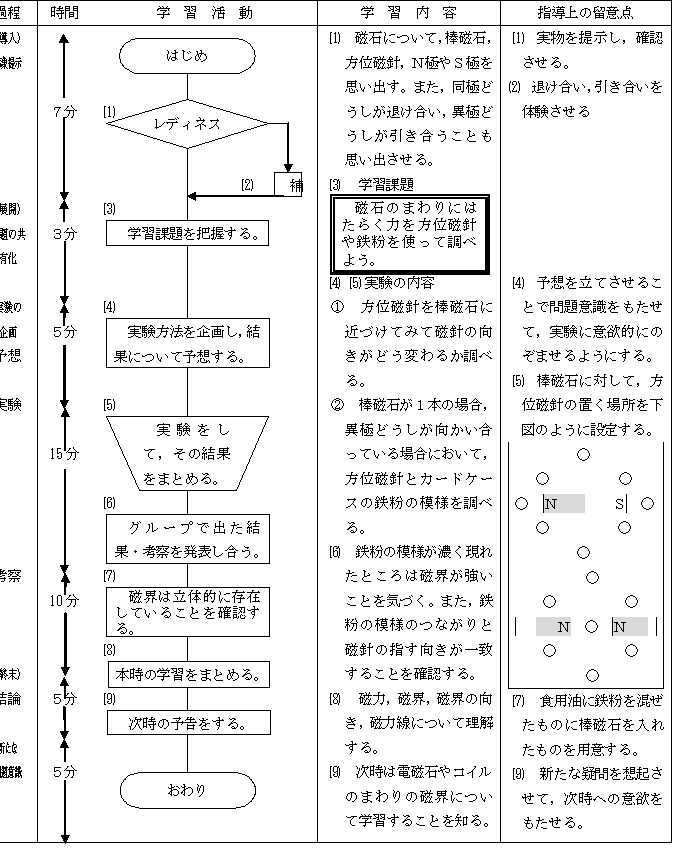
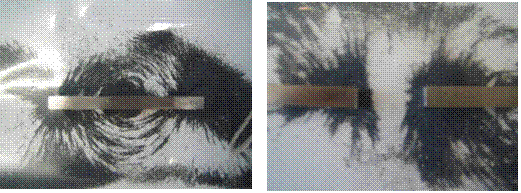 の教具を使うことによって,この点は解消できたようだ。ただ,砂鉄が全体的に均一に散らばることは案外難しく,右図にもあるように全体的に磁力線を描かせることはできなかった。生徒は「N極,S極の両端付近に砂鉄が集まり,濃く模様が現れていることから磁石の力が特に強い」という考察をしていることから,当初の目的は達成できたのではないかと考える。
の教具を使うことによって,この点は解消できたようだ。ただ,砂鉄が全体的に均一に散らばることは案外難しく,右図にもあるように全体的に磁力線を描かせることはできなかった。生徒は「N極,S極の両端付近に砂鉄が集まり,濃く模様が現れていることから磁石の力が特に強い」という考察をしていることから,当初の目的は達成できたのではないかと考える。