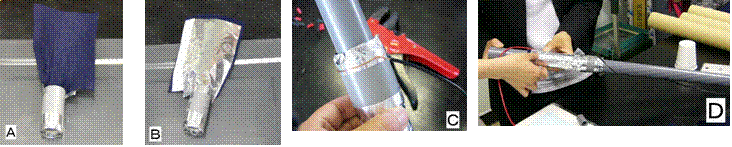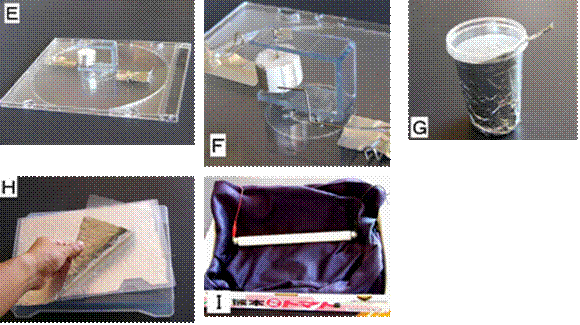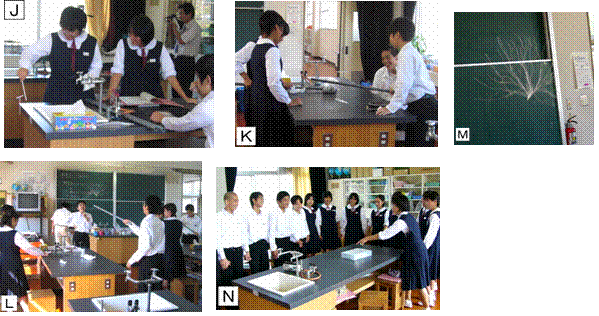|
1 研究に取り組んだ観察,実験(3 電流) 1分野上 電流(電流の流れ) 「静電気を調べてみよう」 2 観察,実験のねらい 生徒は,この単元で初めて電気に関する基礎的な概念を学ぶ。現行の学習指導要領では「日常生活と関連づけて,電流や磁界についての初歩的な見方や考え方を養う」という視点から,単元のはじめに身近な電気の例として静電気を取り上げ,生徒の興味・関心を引き出し,その後の電気回路や電流と電圧の関係などの学習につながる展開となっている。ここで再び内容を確認すると「異なる物質同士をこすり合わせると静電気が起こり,帯電している物体間では,空間を隔てて力が働くこと及び静電気と電流は関係があることを見いだすこと」と書かれており,下線部の点について,教科書の静電気に関する単元の終わりの部分にまとめてある。しかし,生徒の側からこの点を確かに実感したという反応は,なかなか返ってこない。 そこで,単元の導入として静電気の不思議さや面白さを体験させ,生徒の興味・関心を高めるとともに,静電気と電流との関係に気付かせる授業展開を確立したい。 3 観察,実験の実際と問題点 静電気を発生させる手段としてバン・デ・グラフ型静電高圧発生装置があれば,帯電によって髪の毛が逆立つなどの現象を体験させることで効果的な導入が期待できる。テレビ番組等で実験の様子を見たことがあると答えた生徒もいた。しかし,バン・デ・グラフ型の起電器は高価(15万円程度)で簡単に購入できない。教科書に紹介されているストローを使った実験は,手軽にできる反面,ややインパクトに欠ける。また,塩化ビニールのパイプをティッシュペーパーでこする方法がよく用いられるが,発生させる際に多量のティッシュを消費し,しかも静電気の発生量は,その日の気象条件などに左右される。多少悪い条件でも安定して静電気の発生ができる教具の開発が望まれる。さらに,静電気を視覚的にとらえるために,静電気モーター(フランクリン・モーター)を提示したい。プラスチックのコップを使った静電モーターの作り方が指導書等でも紹介されているが,空気が乾燥した日でないと回らない。いつでも確実に元気に回る静電気モーターが必要である。 4 観察,実験の改善のポイント,開発した教材教具 まず,静電気発生装置の製作にあたって,こすり合わせる物質として何と何を組み合わせるかが課題となるが,教育センターの短期研修講座や来所研究で塩化ビニールのパイプとフェルト布を組み合わせた棒起電器の作り方を教わった。製作の流れは次のとおり。 ① 長短2本の塩化ビニールのパイプを準備する。 ② 短い方のパイプに約15cm四方のフェルト布の一辺を両面テープで貼り付ける。 ③ そのフェルトに台所用アルミテープを貼り付ける。 ④ 短いパイプに集電用のアルミテープを巻き,切り込みを入れて集電極とする。 ⑤ 集電部とフェルト部に赤色・黒色のリード線とみのむしクリップをつける。 短いパイプを左手で握り,右手で長いパイプを往復運動させる。摩擦によって塩化ビニール表面に生じた-の電気を集電部で集めて黒色のリード線に導く。パイプを往復させることで,連続して摩擦電気を取り出せるようになる。
次に,小型静電気モーターの製作を行った。 一般的に紹介されているプラスチックのコップとアルミはくを使った静電気モーターは,手軽に作ることができる反面,回転する部分が大きく回転速度がやや遅い。また,条件が悪いと回らないこともある。フィルムケースを使った改良版の作例もあるが,今回の小型静電気モーターは,回転部の軽量化と摩擦の低減を行い,わずかな静電気でも非常によく回る。回転子の作り方や各部の寸法などは,平成18年10月発行の鹿児島県総合教育センター指導資料「理科 第258号」に掲載されている。 さらに,「静電気がたまった」ことを生徒に実感させるため,いわゆる「百人おどし」と蛍光灯を点灯させる実験を授業に加えることにした。そのためには,簡易ライデンびんの製作が必要である。「たまった静電気を流す」場面で,生徒に+極と-極があることに気づいてほしいので,クリアフォルダ,アルミ箔,クリップを用いた「ポリプロピレン・コンデンサ」を使うことにした。
5 実証授業の流れと結果及び考察
今回の授業は10月中旬に行ったため,空気が乾燥した状態で実験をすることができた。 本来の進め方であれば,7~9月の高温多湿な気候の中で実施しなければならない。 静電気の実験は,湿度や埃,汚れなどの条件に左右されるため,前日から理科室の環境維持に気を配る必要がある。 授業直前に導入部分で使うストローの事前の実験では,しりぞけ合うはずが引きつけられてしまった。ストローを交換したりエタノールの噴霧や摩擦を繰り返しても改善されず焦った。試行錯誤を繰り返し,最終的に使用するストローの色とその組み合わせに問題があるのではないかという結論に達した。結局,同色のストローを使うことで,期待されるような「しりぞけ合う」現象が観察できた。
6 実証授業の成果と課題 やや急いで進めた授業だったが,終末部分(まとめと感想を書く時間)は,ほぼ予定通り確保でき,次の授業につなげることができた。途中,板書や発問によって実験の結果を確認したり,考察を行う場面を設けたが,静電気のもつ極性,静電気によって物体が帯電すること,電気が流れる道筋をつくることによって電流が流れることなどの理解を促すことができた。ほとんどの生徒が「楽しかった」,「面白かった」,「不思議だった」といった感想を書いている。実験がテンポ良く進んだこと,それぞれの実験が成功したことも大きな理由だと考えられる。今回作成した教具のうち,棒起電器は安定して静電気を起こすことができた。また,小型静電気モーターは,ほとんど調整することなく使用しても常に高速で回転した。さらに,すべての生徒の心に残った「百人おどし」では,安価で抜群の静電気保持力のあるポリプロピレン・コンデンサが有効であった。 授業全体を通して,生徒が生き生きとした表情を見せたのは,やはり生徒自身が観察,実験をする場面である。生徒が主体となって活動を行う場の設定を心掛けたい。
◎ 今後の授業改善に向けた課題 ①
ストローの実験 教科書にも紹介されている実験である。一般的にポリプロピレン製のストローの場合,ストロー側が負極(-),ティッシュペーパー側が正極(+)になるが,ストローの種類,汚れ,取り扱い方などによっては,-ではなく+に帯電する場合がある。また,ストローの右端と左端で帯電した静電気の極性が違うということもあるようだ。簡単に見えてデリケートな面があった。予備実験や事前の確認が必要である。 ②
はく検電器の使い方 今回の授業では,はく検電器を帯電させて,指で触って電気を逃がす実験を行ったが,はく検電器がなかなか電気をためない,触っても電気が逃げないというトラブルがあった。予備実験ではうまくいったが,授業での演示実験の際,生徒が見やすいように木製のイスの上にはく検電器をのせて実験をしたため,イス(木)から漏電したと考えられる。また,はく検電器のガラス部分や首の部分が汚れると検電能力が下がる。 ③
塩化ビニールのパイプの使い方 パイプを擦るときに,ティッシュを惜しまずに2~3枚重ねてパイプをやわらかくつかむ。パイプを往復運動させるのは右手,ティッシュは左手となる。左手を強く握りすぎるとティッシュが破れたり,汗などの水分がパイプに付着してしまう。 姶良町立山田中学校 森 信浩 |