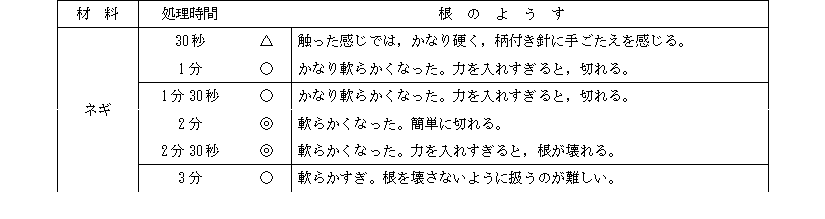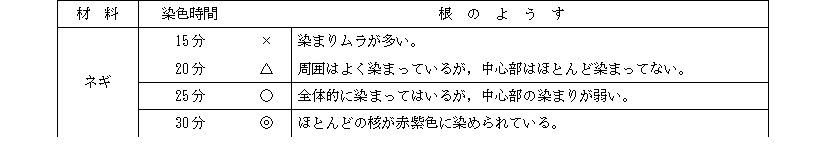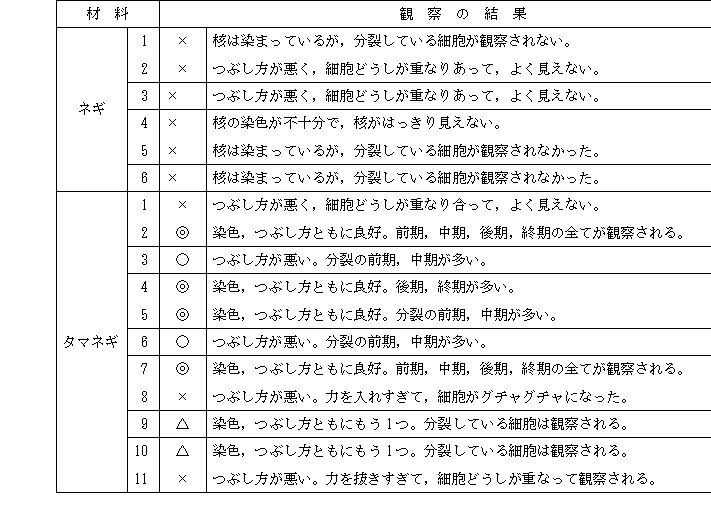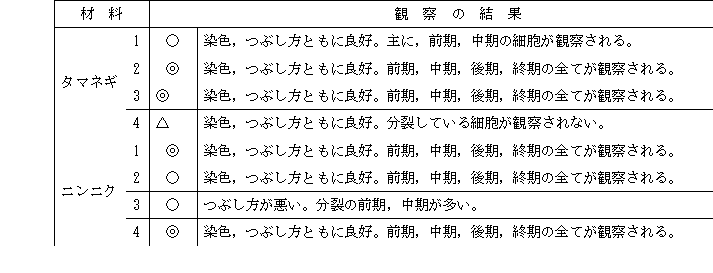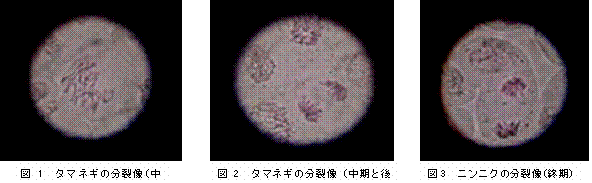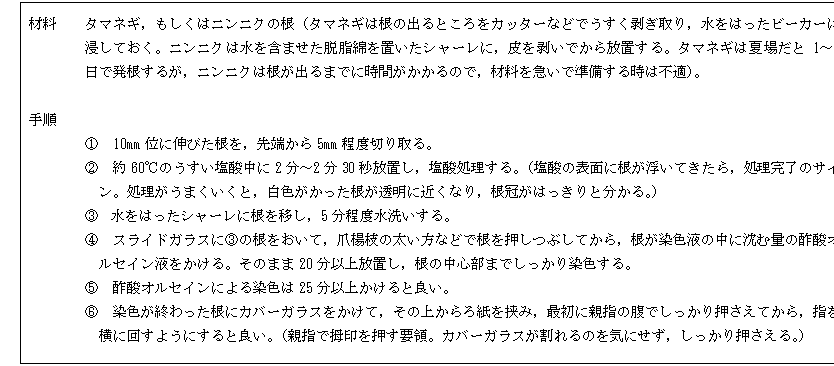|
1 研究に取り組んだ観察,実験(5 生物の細胞とふえ方) 細胞分裂を確実に観察する方法 2 観察,実験のねらい 理科授業に対する生徒の要望には,「観察,実験をできるだけたくさん実施してほしい。」というものが最も多い。 そして,この単元もいくつかの観察を通して,細胞というミクロな視点から生物を学習するところであり,中でも「生物の成長と細胞の増殖を関連づけて考える部分」は,重要かつ難解なところになる。 したがって,①核の中の染色体が見える,②染色体が分かれている過程(途中の段階)が見える,③細胞分裂の異なる過程が見える,という①〜③のすべてを一度に満たす方法を確立できれば,生徒に生物(生命)を観察する楽しさを味わわせることができる。さらに興味ある観察,実験で得られた事実から考察を導くことが,基本的な学力の定着にもつながっていくと考えられる。そこで,この観察が確実に行える方法を確立したい。 3 観察,実験の実際と問題点 (1) 方法について 教科書には,先端から5mm程切り取ったタマネギの根を,60℃のうすい塩酸で1分間あたためてから水洗いし,酢酸オルセイン液で3分間染色する方法が記載されている。 これまでの観察では,①塩酸処理が不十分で細胞をかい離できない,②染色が不十分で核がよく見えない,③根の押しつぶしが上手くいかずに細胞どうしが重なり合う(または,細胞が完全に壊れる)など,うまくいかないことが多かった。 (2) 材料について (1)で述べたように,教科書の説明ではタマネギの根を用いているが,今までの失敗からタマネギが本当に細胞分裂の観察に適しているのか,タマネギの他に観察に適した材料がないのかを調べるために,(1)の結果から再構成した手順を使って,観察に適した材料を見つけることにした。 4 観察,実験の改善のポイント まずは,観察の手順を確立するために,上述の方法の①塩酸処理の時間,②染色の時間について検証した。 2回目は,初回で再構成した手順により,この観察に適した植物を検証することにした。 (1) 観察1回目 (7月28日 於:教育センター) ・ 材料 7月26日から発根させたネギの根(種子から),タマネギの根(りんぺんから)。 ・ 検証① 約60℃の1mol/L塩酸(約3.5%)での処理時間を30秒刻みで設定し,処理後の根を調べる。
◎:多く確認できる ○:確認できる △:確認できるが数が少ない ×:確認できない ・ 検証② 酢酸オルセイン液での染色時間を15分から5分刻みで設定し,染色後の根を調べる。
・ 検証③ タマネギが観察に適しているのか,タマネギ以外に適した材料はあるのか。(塩酸処理2分30秒,酢酸オルセインによる染色25分で,処理方法を統一した。)
(2) 観察2回目(8月22日 於:加世田中学校 理科室) ・ 材料 8月20日に発根したタマネギの根(りんぺんから),8月21日に発根したニンニクの根。 ・ 方法 (塩酸処理2分30秒,酢酸オルセインによる染色25分で処理方法を統一した。)
今回の観察で,実際に得られた映像が下の図1〜図3である。
5 実証授業の成果と課題 3年生の授業では,この内容はすでに学習が終了していたため,実証授業での成果確認はできなかった。 そのため,観察後の生徒の率直な感想や,今回見つけ出した方法が生徒実験に適するのか,観察結果が分かりやすい考察を導く手助けになっているかどうかといった細かいところまで追究できなかった。 来年度以降に3年生の授業や1年の選択を担当した時には,今回の方法で観察を実施し,成果を検証したい。 6 研究のまとめ 「細胞分裂が確実に見える観察方法」は以下のとおりである。
南さつま市立加世田中学校 重岡 有 |