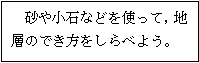|
単元名 |
6年生 大地のつくりと変化 |
|||
|
単元の目標 |
○ 水のはたらきでできた地層のできかたを考え,水槽に土を流しこむ模擬実験を通して,地層のできかたを理解することができる。 |
|||
|
過程 |
学習の活動 |
時間 |
教師の支援・対応 |
|
|
つかむ |
1 前時の授業から,「地層」という言葉の意味について確認する。 2 地層の写真や教師が作った地層を見て,小石や砂,粘土などがどのように積み重なっているのか考える。 3 学習課題をとらえる。 |
10分 |
○ 地層という言葉を教科書で読ませ て確認させる。 ○ 児童が見やすいように,教科書の 写真を拡大して黒板に掲示する。 ○ 地層を作ることに興味がもてるよ うに,教師が作った地層を見せる。 |
|
|
見通す |
4 小石や砂を見て,層はどのようにできるのか予測する。 ・ 班ごとに,予測を画用紙に描く。 |
10分 |
○ 予測を書きやすいように,水槽と空き瓶の絵が描いてあるワークシート(画用紙)を配る。 |
|
|
調べる |
5 砂や小石などを,水の中に流し込んで層ができるか調べる。 ・
実験装置を組み立てる。 ・
材料を選ぶ。 ・
水槽と空き瓶を使った実験を する。 ・
層ができるまで観察し,ノートに記録する。
|
20分 |
○ 実験装置の組み立て方や方法を確実に理解させるために,教科書で確認させたあと,教師が実際に行う。 ○ 児童が装置を組み立てた後,間違いないか,危ない所はないかを確認する。 ○ 児童が楽しく,意欲的に取り組めるように,小石・レキなどを準備し,自由に選ばせる。 ○ グループで協力しながら正しく実験を行っているか机間指導を行う。 |
|
|
深める |
6 地層のでき方を発表する。 ・
画用紙に実験結果を描き,カードを使って発表する。 7 地層のできかたについてまとめる。 |
5分 |
○ 実験の予想と結果が比べられるように,各班に予想と結果を並べ黒板に掲示する。 |
|
|
評価 |
○ 水のはたらきでできた地層のできかたを考え,水槽に流し込む模擬実験を通して,地層のできかたを理解することができたか。 |
|||
|
<成果と課題> 1 地層の堆積実験を通して,水のはたらきによる地層の重なり方を理解させることができた。 2 時間が不足しがちなので,二時間続きで行う方がよい。 |
||||
|
(大崎町立野方小学校 教諭 岩﨑 真由美) |
||||