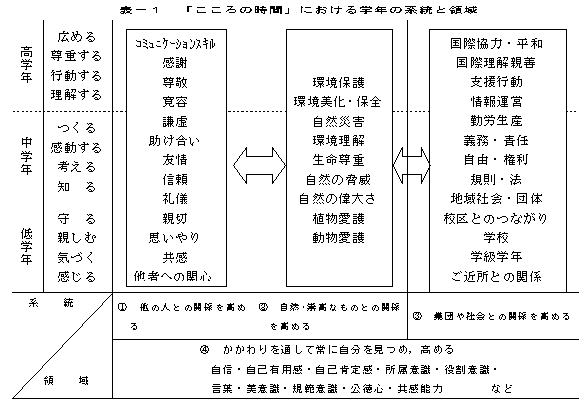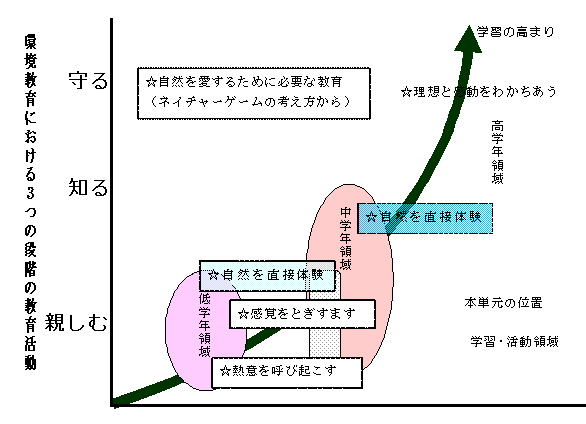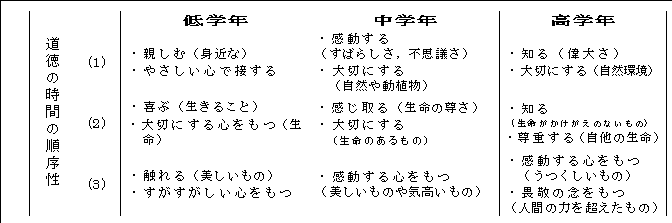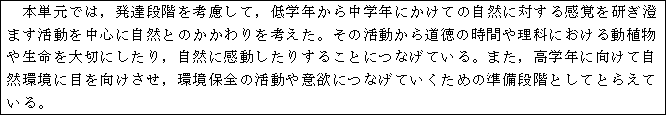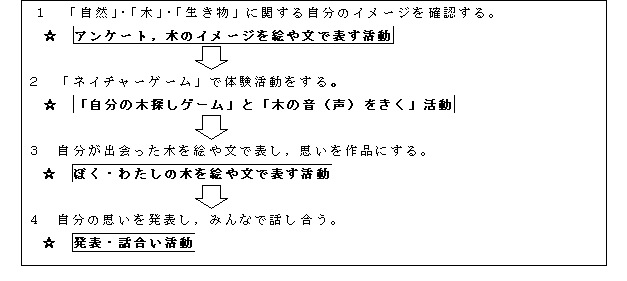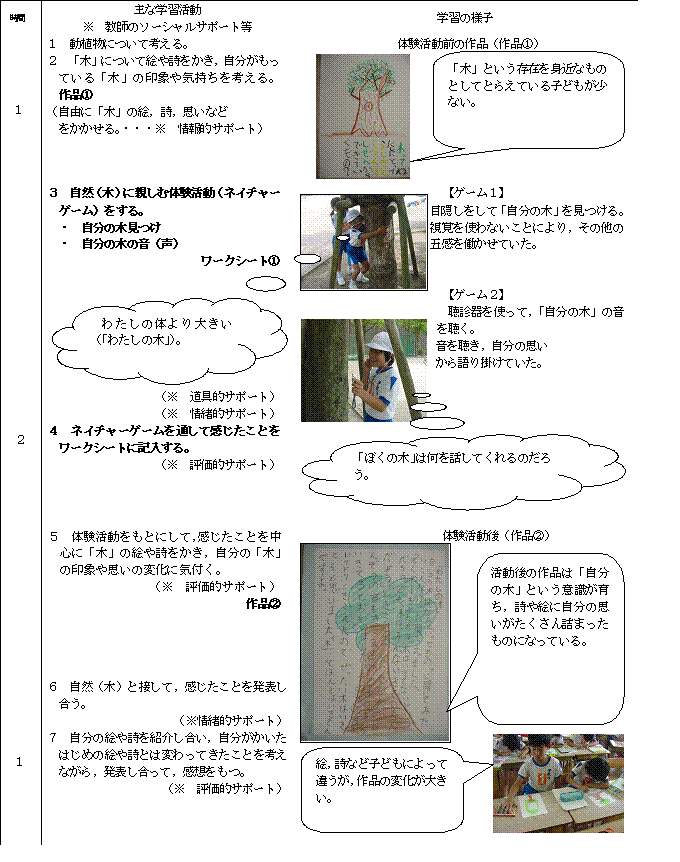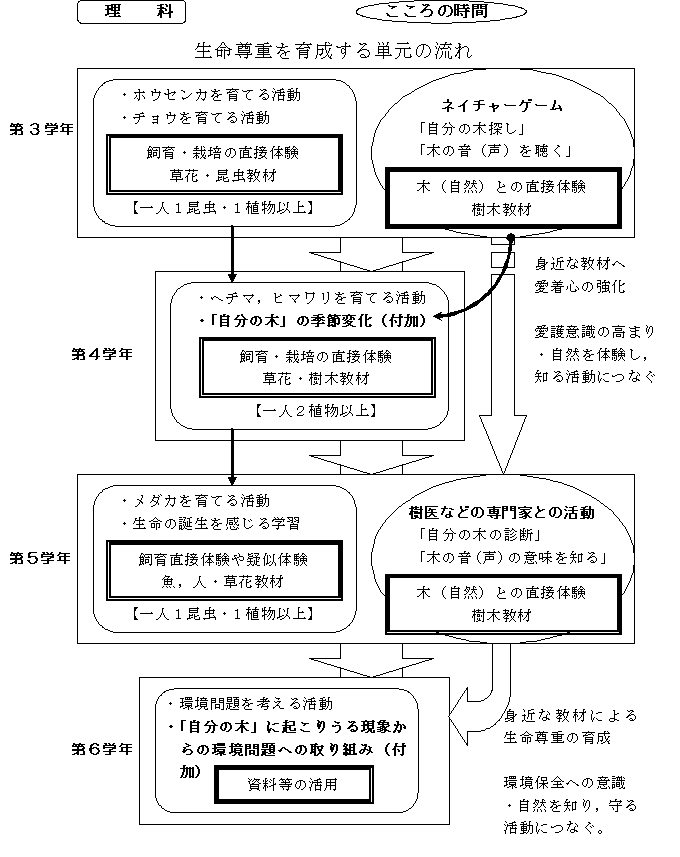|
基礎理科講座 研究報告書 鹿児島市立伊敷台小学校 教諭 加籠六 琢朗 1 主 題 「自然を慈しむ態度を育てる子どもの育成」
2 単元名 第3学年(理科) 「チョウをそだてよう」 こころの時間(特設) 第3学年「みんな生きている」の時間を通して
3 主題設定の理由 これまでの私の実践を振り返ってみると,子ども主体の問題解決的な授業を展開するために,単元導入やまとめの段階で自然事象に対する驚きや発見などを重視したが,生命尊重に関する見方や考え方の育成まで意識して指導したわけではなかった。 例えば,第6学年の酸性雨による森林破壊の学習においては,酸性雨を1つの事象としてとらえるだけにとどまり,「へー,すごい」等の驚きの言葉を得るだけで満足することがあった。そのため,子どもたちに「木がかわいそう」,「何とかしないと」などの生命尊重につながる環境保全に対する意識が生まれにくく,子ども一人一人が「自然=生きているもの」という自然に対しての畏敬の念や「生きている」という意識をもっていないからではないかと考えた。 そこで,「自然=生きているもの」としてとらえることができるように,理科授業のあり方や他領域などとの関連を考慮した内容や指導などの工夫をしていく必要があると考えた。
4 研究のねらい 本校では,本年度から道徳を主体とし,他教科,特別活動,総合的な学習の時間などとの統合を図った「こころの時間」という特設時間を設定し,体験活動や奉仕活動などの直接体験を通した年間70時間の単元開発の研究を行っている。 「道徳と理科」は,道徳の領域に示されている「主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること」に関連を見出すことができるが,特に理科はそのねらいの中で,「自然を愛する心情を育てる」ことが目標となっており,自然に親しみながら「生命尊重」という態度を育成することができる。 そこで,理科と「こころの時間」の関連を有効に図ることで,「生命尊重」に対するより効果的な教育活動を実践することができると考え,理科教育におけるA区分「生物とその環境」にかかわる目標・内容の「生物を愛護する態度を育てる」という点に注目して,単元開発と指導法の改善を重視した理科教育を進めてくことにした。
5 研究の視点 (1) 理科における「自然とのかかわり」に視点を置き,「生物を愛護する態度の育成」,「生命を尊重する態度の育成」における学年の順序性をもたせる。 ア 理科教育におけるA区分の単元のつながりを明らかにして,「生物を愛護する態度の育成」,「生命を尊重する態度の育成」の必要性・重要性を明らかにしていく。 イ 「こころの時間」との関連をもたせ,より効果的な教育活動の実践を行う。 (2) 「こころの時間」の領域や系統を明らかにしていき,理科との関連を明確にする。 ・ 理科教育と関連する「こころの時間」における「生命尊重・自然を愛する心を育てる」 領域の単元を開発・実践し,理科との関連を密なものにしていく。 (3) 「こころの時間」の開発・実践した単元の有効性や理科との関連を明確にし,子どもの変 容を評価しながら,研究の成果と課題を明らかにしていく。 (4) 理科の授業における教師が提供できるソーシャルサポート ア 情緒的サポート 実験,観察,発表場面などにおいて,「大丈夫だよ。落ち着いて取り組んでごらん。」,「ここを工夫すると,もっと分かりやすくなるよ。」などの情緒的働き掛けを行うことで,学習に対する安心感や意欲を高める支援を行う。 イ 情報的サポート 実験,観察器具の使い方,解決のヒント,学習を進めるためにどんな調べ方をすればいいかなどの情報を提供する支援を行う。 ウ 道具的サポート 子どもが納得・実感できるような実験,観察の提示,ワークシートの活用など学習に必要な道具,グループ編成,座席などの学習環境に至るまでの様々な具体的支援を行う。 エ 評価的サポート 学習活動の過程や結果について,「どこでつまずいているのか,どこを改善すればよいか」,「どのような学習がよかったか」など,教師が子どもの学習への取組を肯定的に受け止め,その評価をフィードバックする。
6 研究の実際
(1) 理科における「生物を愛護する態度の育成」の活動について 「生命尊重」を重視した活動を取り入れるために,今回の単元 では,まとめの段階で観察記録や子どもへの発問などを工夫した。 (2) 3年単元「チョウをそだてよう」の実践 ア 実践内容 本単元において,まとめの段階でチョウの一生を劇や紙芝居 にしたり,これまでの観察記録のまとめをもとに発表したりす る活動を行った。 まとめでは,子どもの話合いを重視し,これまでの学習の成 果を発表するように指導した。9グループ中,四つの班で劇, 三つの班で紙芝居,二つの班で観察記録をまとめた発表を行う ことになった。 イ 実践結果 「生物を愛護する心情」に関する内容の表現内容になっているかの観点から評価すると,「劇」を通した発表が最も顕著であった。例えば,アオムシになりきって気持ちを考えたり,自分に置き換えて(擬人化・同化)考えたりする子どもが多かった。また,発表を見た子どもたちからは,「生命に関する大切さを感じた」という内容の感想が多かった。 ① 劇によるまとめ 生まれる瞬間の場面やアオムシコマユバチに寄生されてしまう場面,脱皮の時の気持ちを表現する場面などアオムシになりきって考えていた。「命」という言葉が活用されたのも,この発表の形式が多く,発表者も発表を聞く側も「命」という視点で考えることができた。 一方,仲間と出会った時の気持ちや卵を守る成虫の場面を発表に取り入れたグループもあり,観察によるものだけでなく,内面的な観点から発表する光景も見られた。 ② 紙芝居によるまとめ 成長の段階を発表したものが多く,同時に観察記録を生かした細やかなスケッチが多かった。また,体のつくりやはたらきなど,これまでの学習を生かした発表が多かったが,飼育の失敗の経験を発表した子どももいた。 ③ 観察記録によるまとめ 成長の過程やさなぎの期間など時間を意識した発表もあり,成長の様子がよく分かる発表ができた。また,観察で発見したことや驚いたことなどを感想としてまとめていた。 (3) 研究1の成果と課題 ア まとめの段階で劇化等を活用することは,「命」を考える上で,とても有効な方法であるが,このような発表方法をとる場合には,これまでの学習で分かったことや発見したことなどを生かすことが大切である。 イ 子どもに観察や調べたことの事象をもとに発表させると,科学的見方・考え方だけでなく「生命を尊重する態度」をも育成される。これらが十分でない場合は,経験をもとにした単なる想像だけの内容に終わる場合が多い。 ウ 子どもには飼育を通した,生き物に対する関心をもたせることが重要であり,例えば自分のアオムシの成長を観察させることは自然への愛着心を育成するには大変有効である。 エ 発達段階に応じた体験活動が必要であり,理科においても系統的な「生命尊重を育てる体験活動」が重要になる。そのためには,ただ単に授業を展開するだけでなく,学習の中に「生命尊重」を意識した体験活動が必要である。 オ 理科の授業においては,「生物を愛護する態度」を育成するための体験活動も積極的に取り入れながら資質・能力や科学的な見方や考え方を育成していくことを重視し,その他の教育活動との連携も図っていくことが重要である。
(1) 新たに開発した単元の目標 学習指導要領の目標やA区分における「生命尊重」を基に,単元や教材としての自然を学年 別にまとめたのが別添資料1である。目標においては「生物の愛護」から「生命の尊重」まで,中学年から高学年への発達特性を踏まえた目標が設定されている。 単元の学年系統は,資質・能力や科学的な見方や考え方の育成を重視した内容構成になって いる。これらは,飼育・栽培,実験,観察などを通して育成していく内容であるので,理科と「こころの時間」との連携を図り,体験活動を核としながら自然を愛護する心情を育てるような内容を工夫していくことにした。 今回開発した単元は,「木」(自然)に触れる体験活動から「生きている」ことを感じ,「生物を愛護する態度を育てる」ことができるようにしたものである。そこで,体験活動としてネイチャーゲーム(別添資料2)を取り入れ,校内の樹木を「自分の木」として決めさせ,「自分の木」と語る(聴診器を使って音を聴く)活動を行わせた。 ア 本単元の目標 ○ 植物(木)にも自分たちと同じようにかけがえのない命があり,身のまわりには,たくさんの命があることを理解することができる。 ○ 木に触れる活動を通して,植物(木)も生きていることを感じ,友達の感じ方と自分の感じ方を比べながら,自然を愛護する気持ちを高め,自然を育てていきたいという行動力を身に付けることができる。 (2) 「こころの時間」の領域と系統 現段階における「こころの時間」における領域と系統は表―1であり,②の領域は理科で扱う内容や態度の育成に大きくつながりがある。
(3) 本単元の発達特性における学習段階の位置づけ
【本単元で参考にした図書】 ○参考図書 構成的グループエンカウンター辞典 株式会社図書文化社 ネイチャーゲームでひろがる環境教育 サンメッセ株式会社 小学校 心を育てる授業ベスト17 株式会社図書文化社 (4) 「こころの時間」の実際 ア 開発単元における主な学習の流れ
イ 開発単元における学習活動の様子 単元の指導計画(全4時間)
(5) 研究2の成果と課題 ア 「生物愛護・生命尊重」の態度を育成するためには,直接体験を重視しながら,理科の単元に「こころの時間」のような新たな単元を補足しながら,指導することは有効である。 イ 別添資料3にもあるように第4,6学年においては,新たな単元を開発するのではなく既存の単元に活動や取り組みを付加内容として取り入れ,学年間のつながりをより密なものにすることも重要である。 ウ 子どもにとって,「自分の○○」という愛着を強めるような教材の提示は,自然事象を身近なこととしてとらえることにつながり有効である。
7 研究のまとめ ア 飼育・栽培,観察などの活動を通して得られた生物(教材)に対する思いを,まとめの段階で劇や紙芝居などで発表することは,「生物を愛護する態度の育成」に非常に有効であるが,観察等で得た知識や科学的な見方・考え方を生かすための授業の高まりが重要である。 イ 理科の授業においては,科学的な見方・考え方を育成していくことが,「かわいい」,「かわいそう」などの情緒的な感想から,生物を生命のあるものとして大切にしたいという「生物を愛護する態度」まで高める。 ウ 発表や体験活動の際に,思い通りに活動できない子どもには4つの観点のサポートをしたところ,子どもたちは協力し合いながらグループの役割を果たすことができた。 エ 本単元を終えた子どもたちは,少なくとも校庭にある木を「自分の木」として愛着をもって眺めたり,触れたりしている様子が日常でも見られるようになった。また,「○○くんの木」という表現も日常生活で使われるようになった。これは,「木」というものがこれまでより身近なものとして意識できてようになったものと考える。 今後は,さらに実践を重ねながら,現在の3年生の子どもたちが,6年生を迎えたとき,理科の学習でどのような言葉で表現し,どのような考えから環境問題に取り組もうとするのかをみて,本研究の最終的な成果としたいと思う。
別添資料2 ネイチャーゲーム実施資料(第2,3時) 1 「わたしの木探し」ゲーム(30分) 「この校庭の中に,あなただけの『木』が必ず1本だけあります。その『木』を探してみましょう。その木があなたを呼んでいるのですよ。』(ゲーム説明) 【ゲームの内容】 (準備するもの)アイマスク,ワークシート①,探検バッグ,筆記用具 ① 校庭のある場所で,二人組みをつくらせる。 ② 一人がアイマスクをして,何も見えない状態になる。 ③ アイマスクをした子が,思った方向をむく。もう一人(パートナー)がその方向に,大 きな木のほうに連れて行く。(数回,回ってみるのもよい。見えている一人が選んで連れて行くだけでもよい。) 《注意》目隠しをしているので,パートナーの子どもは,足元にも注意をする。 ④ 木に連れて行ったら,まず木に手を触れさせ,体全体で触れるように誘導する。そこで パートナーが様々な情報を与えるようにする。擬人化した言い方で,葉や枝を手や腕などに例える言い方などもよい(木の大きさ・色・かたちなど)。 ⑤ アイマスクをした状態でしばらく「木」を感じ(対話し)たら,スタートした場所につ れて戻る。 ⑥ アイマスクをはずし,自力で「木」を見つけに行く。触れた感覚やにおいなど自分で見 つけるようにする。迷ってしまいそうだったら,パートナーからおおよその方向を聞く。 ⑦ しばらくは,対面の喜びを味わいさせる。 ⑧ 交代して同じように行う。 【ワークシート記入(5分)】 「あなたを呼んでいるあなたの『木』を見つけることができましたね。どんな木でしたか。」 ① イメージを膨らませながらワークシートに印象を一言記入する。 ② さわった感じを記入する。 2 「木の声をきく」ゲーム(20分) 「あなたの木は,何か言っていませんでしたか?声を聞くことができないのかな?木の声はとっても小さな声なのかもしれませんね。静かにして聞かないといけないでしょう。どうすれば聞こえそうですか?』 【ゲームの内容】 (準備するもの)聴診器,ワークシート①,探検バッグ,筆記用具 ① 木に抱きついて,耳を接して聞いてみる。 ② 聴診器を静かに当てて音を聞いてみる。 ③ パートナーに代わりながら,ワークシートに「木」の音や声を書く。 ④ 交代してもう一人の「木」で同じ活動をする。
「どんな声が聞こえたかな。どんなことをいっていたかな。自分の『木』にさよならの手をふって教室に帰りましょう。』 3 思いをそのままにして,すぐに絵を描いたり,詩を書いたりする活動に入る。(残り時間20分ぐらい)時間をかけすぎないようにクレヨンで描くようにする。
別添資料3 生命尊重のこころを育成する理科とこころの時間の連携・関係図
|