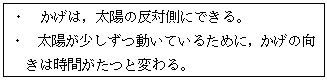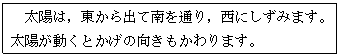|
単元名 |
3年 日なたと日かげのちがい |
|
|
単元の目標 |
○ 日なたと日かげの地面のようすに興味をもち,太陽の光が当たっている地面と当たっていない地面のようすを比較しながら調べ,日なたと日かげの地面のようすには違いがあることをとらえることができるようにする。 ○ かげの位置の変化と太陽の動きとの関係を調べ,かげの位置は,太陽の動きによって変化することをとらえることができるようにする。 |
|
|
学習の活動 (児童の素朴な見方や考え方) |
教師の支援・対応, (納得実感させるために必要な観察,実験) |
|
|
「調べる方法」 1 かげができるように棒を立てた観察用 具を作る。 2 2時間ごとに,かげのできた方向と太 陽の向きを記録する(午前8時,午前10時,正午,午後2時,午後4時)。 3 方位磁針を使って方位を確認する。
「観察用具を作ろう」 1 板に画用紙を貼り,割り箸を立てる。 2 割り箸は倒れないように画用紙の裏か ら画鋲で固定する。 3 観察をしよう。
C;「かげを写した線が動いている。」 C;「真ん中に立てた割り箸を中心にして動 いている。」 C;「太陽と反対の向きにかげができてい る。」 C;「太陽も時間ごとに動いている。」 |
○ 建物等で日かげにならないように,1日中日なたになる場所で実験を行う。 ○ 記録する場合は,かげのできた向きだけでなく,できたかげの長さにも着目させ,記録するように指導する。 ○ 午前中から午後まで観察し,正午には必ず観察するように指導する。 ○ 方位磁針の使い方を理解させ,正しく測定・記録させる。
○ 紙に方位を書かせ,方位磁針で方位を合わせて記録させる。 ○ かげの線は鉛筆で,太陽の向きは赤鉛筆で記録させる。
○ 各時刻のかげの方位を確かめる。 ○ かげは,太陽と反対の向きにできることを理解 させる。 ○ かげの向きだけでなく,長さにも着目させ記録させる。
|
|
|
C;「どうしてかげの長さが違うのかな。」 C;「正午は日光が真上から当たっていた よ。」
「調べる方法」 1 真っ暗にした室内で懐中電灯を太陽にみたて,前の実験で使った観察用具に光を当てる。 2 記録した線のとおりにかげができるように懐中電灯を動かす。
C;「太陽が割り箸の真上にくるとかげが長くなるよ。」
C:「太陽が低くなるとかげがどんどん長くなるよ。」 3 実験の結果から太陽の一日の動き方とかげの向きについてまとめる。
4 教科書の「理科のひろば」を読み,太陽光を利用しているものについて話し合う。
|
○ 正午のかげの向きと長さに着目させる。 ○ 太陽の動き方が,かげの長さにも関係があることを考えさせる。
○ 光が入らない部屋(暗幕を閉めた理科室等)で実験を行うのが望ましい。 ○ 方位磁針で室内での方位を確認し,きちんと合わせておく。
○ 教科書の写真を見て,理解を深めさせる。
|
|
|
(屋久町立小瀬田小学校 教諭 鹿島由美子) |
|