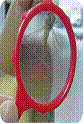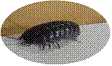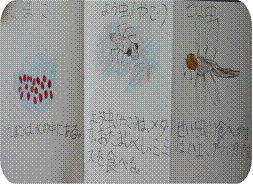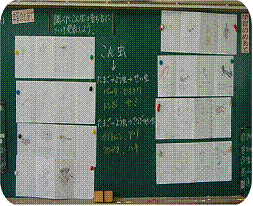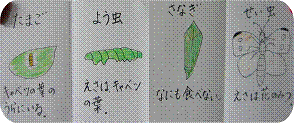|
�P���� |
�R�N�@��������ׂ悤 |
|
|
�P���̖ڕW |
���@��O�ɂ��鍩���ɋ����������C���낢��ȍ������������āC�����̐H�ו��Ƃ��݂��ׁC�����ɂ͐A����H�ׂ���C��������݂��ɂ����肵�Đ����Ă�����̂����邱�Ƃ��Ƃ炦�邱�Ƃ��ł���B ���@���낢��ȍ����̂��炾�̂���ׁC��Ɋw�K�����`���E�̈炿���Ɣ�r���C�����ɂ́C�c������匂��o�Ȃ��Ő����ɂȂ���̂����邱�Ƃ��Ƃ炦�邱�Ƃ��ł���B |
|
|
�w�K�̊��� �i�����̑f�p�Ȍ�����l�����j |
���t�̎x���E�Ή� �i�[���E���������邽�߂ɕK�v�Ȋώ@�C�����j |
|
|
�P�@������������ (1) �ǂ�ȏ��ɂǂ�Ȓ�������̂��l����B �@ ���@���ނ�Ƀo�b�^������B �@�@ ���@�r�ɃA�����{������B ���@����y�ɒ�������B
(2) ��������������B
���@���ނ��Ԃł���������C���䂷�����肵�Ȃ��疲���ɂȂ��āC�����������Ă����B (3) ���܂������̐H�ו��₷�݂��ɂ��Ē��ׂāC���\����B ���@�Z�~�͏����Ȓ���H�ׂ�Ǝv���Ă����B�̂��邪�H�ו��Ƃ͒m��Ȃ������B ���@�o�b�^�͑��Ɠ����F�����Ă��邩��C�G�Ɍ�����ɂ����B�@ (4) ���̐H�ו��Ƃ��݂��Ƃ̊W���܂Ƃ߂�B |
���@�q�ǂ������̍����ɑ���S�����߂邽�߂ɁC�s�̂̍����͌^�����B ���@���O�ɍ����̏W������ꏊ�̉����ɍs���C������x�C�̏W�ł��鍩����c�����Ă����B
���@�̏W�ɍs���O�ɁC���S�w���i�@�n�`��ђ��ɗv���Ӂ@�A����ł̉���ɒ��Ӂ@�B�댯�Ȃ��Ƃ����Ȃ����Ɓj���s���B ���@�̏W���������́C�������ɓ���Ċw�Z�܂Ŏ����A��C���̏ꏊ�ɖ߂��O�Ɏʐ^���B��C�����Ɍf�������B �����V���`���E�E�V���E�����E�o�b�^�E�C�i�S�E�J�}�L���E�e���g�E���V�E�����V���`���E�E �c�}�O���q���E�����E�V�I�J���g���{�@�Ȃ�
���@���ׂ���@�́C���ȏ���}�����̐}�ӂ��g���Ē��ׂ������B ���@�q�ǂ������́C�u���݂��v�Ƃ������t�Ɍ˘f�����B�����ŁC�u���̍�������������ꏊ�v�̂��Ƃ��ƌ����������B ���@�H�ו��Ƃ��݂��̊W���ɂ��ċC�Â��q�ǂ������Ȃ������̂ŁC�u�Ȃ��C�o�b�^�͑��ނ�i���݂��j�ɂ�������̂��v�Ɩ₢�|����Ɓu�������������邩��v�Ƃ����������Ԃ��Ă����B |
|
|
�����ʂƉۑ聄 �P�@�̏W���������̎ʐ^�������Ɍf���������ƂŁC�q�ǂ��̍����ɑ���S�������ł����B�@ �Q�@�H�ו��i�A���j�Ƃ��݂��̊W�����C�Â��₷�����邽�߂ɁC�A���i�ԁE���E�E�y�j���`����Ă��郏�[�N�V�[�g���������C���̐A���̏ꏊ�ɍ����̖��O�ƐH�ו����������߂�悤�ɂ���ƕ�����₷�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B |
||
|
�w�K�̊��� �i�����̑f�p�Ȍ�����l�����j |
���t�̎x���E�Ή� �i�[���E���������邽�߂ɕK�v�Ȋώ@�C�����j |
|
|
�Q�@���̂��炾������ׂ悤 (1)�@�o�b�^��g���{�̂��炾�̂���ׂ�B ���o�b�^�ɂ��ā� ���@���͂U�{�łƂ��Ƃ�������B ���@���������āC�ڂ��������B ���@�������͂˂�����B ���@�G�o���Q�{����B�@�@�@�@�Ȃǁ@ ���g���{�ɂ��ā� ���@���炾���O�ɕ�����Ă���B ���@�ڂ̒��ɏ����Ȗڂ������ς�����B ���@�����ۂ��Ȃ���B ���@�͂˂������Ƃ����Ă��āC�S������B ���@�����Ȗт���������B�@�@ (2) �_���S���V�̂��炾�̂���ׂ�B ���@������������B ���@���炾������������Ă���B ���@�����ȐG�o���Q�{����B�@ ���@�ǂ����ނ˂Ƃ͂�Ȃ̂�������Ȃ��B�@�@�@�@�@�@�@�Ȃ� (3) �o�b�^�E�g���{�ƃ_���S���V�̂��炾�̂���̈Ⴂ�����[�N�V�[�g�ɂ܂Ƃ߂�B |
���@���O�ɐ��l�̎q�ǂ������ƈꏏ�ɃN���X�̐l�����i�W�l�j�̃o�b�^���̏W�����i�_���S���V���l�����C�g���{�͂P�C�j�B
���@�`���E�̂��炾�̂����z�N�����C�o�b�^�̂��炾�̂���ɂ��ė\�z�𗧂Ă������B ���@���ׂ�ۂ́C�ώ@�̃|�C���g������B �g���{�͈�C�������Ȃ̂ŁC�y�A�ɂȂ��Ċώ@�������B �@ �A�@���炾�̕������ �@ �B�@������͂˂̕t���� �C�@�ڂ���̌` �D�@���̑��ɋC�������Ƃ���
���@�o�b�^�͗c�����������߂ɁC�͂˂��������C�����𐔂���̂���������B
���@�g���{�́C���E���E�����͂�����ƕ�����Ă���C���炾�̂�����m�F����̂ɓK���Ă����B�q�ǂ������́C�g���{�̖ڂɒ��ڂ��Ă����B
���@�_���S���V����l���ɓn���C�o�b�^��g���{�̂��炾�̂���Ɣ�r���Ȃ���ώ@����悤�ɐ��|�������B
���@�_���S���V�͓������߂Ɋώ@���Â炢�̂ŁC���ȏ��̑}�G���g���Ă����̐��͐����������B�N���̂��炾�̂���ɂ��Ă���舵�����B
���@�q�ǂ�����C�u�_���S���V�E�N���́C�����łȂ���Ȃ�Ȃ̂��H�v�Ǝ��₪�������B |
|
|
�����ʂƉۑ聄 �P�@�o�b�^��g���{�ƃ_���S���V�Ƃ�����r�Ώە������ۂɎ�ɂƂ��Ċώ@�ł����̂ŁC�q�ǂ������̊w�K�ӗ~�����������B �Q�@���̍����̂��炾�̂���ɂ��Ă����ׂ�����ƁC���炾�̂���ɂ��Ă̗������X�ɐ[�߂�ꂽ�Ǝv���B
|
||
|
�w�K�̊��� �i�����̑f�p�Ȍ�����l�����j |
���t�̎x���E�Ή� �i�[���E���������邽�߂ɕK�v�Ȋώ@�C�����j |
|
|
�R�@�g���{��o�b�^�̈炿���ׂ悤�B (1) ���������ׂ������̈炿���ɂ��ċ��ȏ���}�ӂŒ��ׂ�B
(2) ���ׂ����Ƃ���p���ɏ����B
(3) ���ׂ����Ƃ\�������C�C�Â������Ƃ��܂Ƃ߂�B
���@���Ȃ��ɂȂ�Ȃ���������B ���@�A�����܂�����Ȃ�Ēm��Ȃ������B ���@�g���{�͐��̒��ɂ��܂������ށB ���@�o�b�^�ƃJ�}�L���͂��Ȃ��ɂȂ�Ǝv���Ă����B�@�@�@�@�@�@�@�Ȃǁ@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
���@���ȏ��ł́C�g���{��o�b�^�̗c�������炵�Ȃ���C�ǂ̂悤�ɐ����ɂȂ��Ă������ώ@������ƂȂ��Ă���B�������C�T�����͂����������S��������Ȃ�������C�o�b�^�̐��������Ƃ̐i��ƍ���Ȃ������肵�āC����E�ώ@���\���ɂł��Ȃ������B ���@��L�̂悤�Ȏ��Ԃ܂��āC�W��ނ̍������q�ǂ������ɒ��C�������炿���ׂĂ݂�����������I�сC���ȏ���}�ӂ��g���Ē��ׂ������B �s���S�ϑԂ̍����i�o�b�^�E�g���{�E�Z�~�E �J�}�L���j�@ �@���S�ϑԂ̍����@�i�n�`�E�J�u�g���V�E�A���E �N���K�^�j ���@���݂��̔��\�̒��ŁC�����̈炿���ɈႢ�����邱�Ƃ��C�Â��������Ƃ����Ӑ}����C�s���S�ϑԂ̍������܂܂�Ă��邱�Ƃ͎q�ǂ������ɂ͒m�点�Ȃ������B ���@���ׂ����Ƃ̂܂Ƃߕ��̗������B��p�����Q���Ȃ��Đ܂�ڂ����C�G�{�̂悤�ɕ�����悤�ɂ����B �@��i�F�����̐����̗l�q �@���i�F�����̗l�q�̊G�@ |
|
|
�����ʁE�ۑ聄 �P�@���ׂ����Ǝv�������̈炿����}�ӂŒ��ׂĂ��������ɁC���ȏ��ɍڂ��Ă��Ȃ��悤�ȓ��e�������Ŕ����ł���Ɣ��Ɋ��ł����B �Q�@�s���S�ϑԂ̍����̈炿��������̓I�ɒm�邽�߂ɁC���S���������鎞���Ƀr�f�I�ŎB�e���Ă�������C�e���r�̊w�Z�����������Ɗ��p�����肷�邱�Ƃ��ۑ�Ƃ��Ďc�����B�@�@�@�@ |
||
|
�i�����c�s���씨���w�Z�@���@�@���@�b�q�j |
||