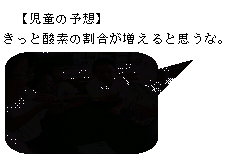|
単元名 |
6年 生き物のくらしとかんきょう |
|||||
|
単元の目標 |
生き物と空気,食べ物,水とのかかわりに問題をもち,これまでの学習や生活経験などを想起しながら,空気中の酸素は植物が出していること,人や動物の食べ物のもとは植物であること,生きている植物だけでなく,枯れた植物も動物の食べ物になっていること,水は生き物にとって不可欠なものであることを,実験したり資料で調べたりして知り,生き物は互いにかかわり合って生きていることをとらえることができるようにする。 |
|||||
|
学 習 の 活 動 |
教師の支援・対応 (納得・実感させるために必要な観察,実験) |
|||||
|
1 学習問題をつかむ。 |
○ 酸素を使うばかりでは,「酸素はなくなってしまうのではないか」という考えから,教科書の挿絵を使い植物が酸素を出しているのではないかと推論させる。 ○ 気体検知管の使い方を再度,復習して実験を行う。酸素用検知管は熱くなるのでゴムのカバーを持つように指導する。 ○ 実験に使用する植物は,理科室で育てている観葉植 物のサンスベリア(トラノオ)を利用した。
○ 光合成が活発に行われる,晴れた午前中に実験を行うようにする。
【評価】 植物に袋を被せ日光に当てて,中の酸素と二酸化炭素の割合の変化について気体検知管を用いて調べ,結果をまとめることができたか[行動観察・ノート]。 ○ 植物は日光に当たると二酸化炭素を取り入れ酸素を出すことを,実験結果からまとめる。 ○ 実験結果から,呼吸や燃焼で酸素を使ってもなくならないのは,植物が二酸化炭素を取り入れ,酸素を出しているからであることをとらえさせる。 ○ 身の回りの植物を増やすとともに,世界中の植物が減らないように努力することの必要性を話す。 |
|||||
|
|
空気中に酸素を出している物 は何だろう。 |
|
||||
|
2 教室内の酸素と二酸化炭素の割合を気体検知管で調べる。
3 植物に袋を被せ,息を吹き込む。 4 袋の中の酸素と二酸化炭素の割合を気体検知管で調べる。 【児童の予想】 二酸化炭素の割合が増えていると思うな。
5 日光に当てて1時間後もう一度,袋の中の酸素と二酸化炭素の割合を気体検知管で調べる。
【児童の予想】 植物が,二酸化炭素を吸って酸素を出したと思う。
6 本時の学習のまとめをする。 |
||||||
|
|
植物に日光が当たると二酸化炭素を取り入れ,酸素を出す。 |
|
||||
|
|
||||||
|
(阿久根市立大川小学校 教諭 西村 新) |
||||||
|
|
|
|
|
|
||