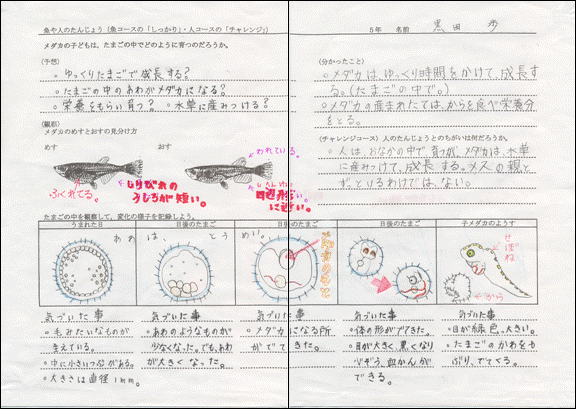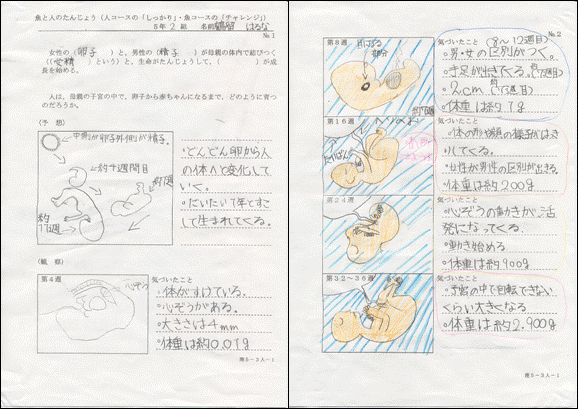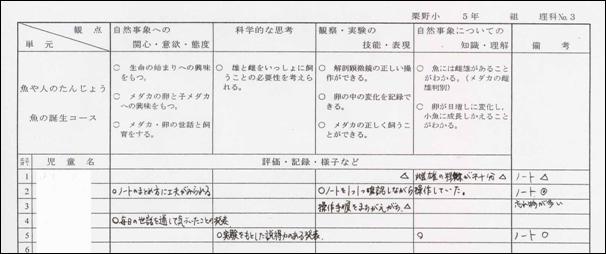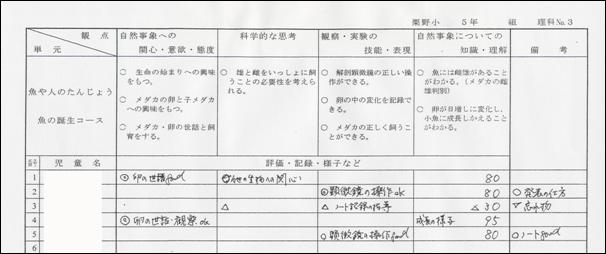|
�{�Z�́C����14�N�x����16�N�x�܂ł̂R�N�ԁC�u�w�͌���t�����e�B�A�X�N�[���v�̌����w����C�����̃h�����^�C����s�s�E���l���w���i�K�n�̒��x�ɉ������w���C��[�E���W�I�w�K�j�E�ꕔ���ȒS�C���Ȃǂ����C�w�K�̊�b����w�т̎��Ԃɉ��������ߍׂ��Ȋw�K�w����W�J���C�X�̊w�͂����コ���邽�߂̎w�����@���P��w���Ԑ��̍H�v�Ɏ��g��ł����B
�@���̒��ŁC���Ȃɂ����Ă͒S�C�Ǝw���@���P�W�łs�s�����̎��Ƃ��s���Ă���B�܂��C�ۑ�I���w�K���[�E���W�I�w�K�ɂ����ẮC�����̋����S���]�Ȃǂ������߂Ɂu�`�������W�R�[�X�i���W�I�w�K�j�v�Ɓu��������R�[�X�i��[�w�K�j�v�ɕʂ�w�K���s���Ă���B
|
�P�@��[�E���W�I�w�K�̎��H
�@�@�{�Z�ł́C�N�Ԏw���v��ɕ�[�E���W�I�w�K�́u�ʒu�t���\�v��Y�t���C��������ƂɁC�W�J�Ă���у��[�N�V�[�g���쐬���C�w���ɓ������Ă���B
�y��[�E���W�I�Ȋw�K�̓��e��z
|
�P��
|
�T�N�@����l�̂��傤
|
�@�@�@���@��
|
�@�@�@�I�@��
|
|
�@��
�@�e
|
�q�@�@��@�@�[�@�@�r�@�@�@�@�@�@�@�@�@�q�@�@���@�@�W�@�@�r
���_�J�̂��܂��̒��̕ω��ׂ�@�@�@��̓��ł̎q�ǂ��̐����̗l�q�ׂ�
|
�y��[�E���W�I�Ȋw�K�̔N�Ԉʒu�t���\�z

�u����l�̂��傤�v�ł́C�P���̖ڕW�ł���w�����̒a������̂��炵���Ɋ������C�������ɂ��悤�Ƃ���x�ɂ��[�����邽�߂ɁC�u���̂��傤�v��S���Ɋw�K�������B���̌�C��[�E���W�I�w�K�ւƂȂ��Ă������B����ɁC����̃R�[�X��I�����������̃R�[�X�ł̊w�K���e��m�邱�Ƃ��ł���悤�ɁC�r�f�I��������������C���ꂼ��̃��[�N�V�[�g���f���������肵���B
�Q�@�W�J��
|
�P����
|
�T�N�@�@�@�@�@����l�̂��傤
|
|
�����̊����Ƌ��t�̎x��
|
|
��������R�[�X�i���R�[�X�����j
�`�������W�R�[�X�i�l�R�[�X�����j
|
��������R�[�X�i�l�R�[�X�����j
�`�������W�R�[�X�i���R�[�X�����j
|
|
���_�J�̂��܂��̒��̕ω��ׂ�B
�i�I���w�K�u���̂��傤�v�̓��e�j
|
�P�@�����̉ۑ��m��B
�@�E�@���e�X�g��]���e�X�g����ɁC������������Ȃ��_��_�J�̂��傤�ɂ��Ēm�肽�����Ƃ��e���ɂ��܂���B
|
�@���_�J�̎q�ǂ������́C���܂��̒��ŁC�ǂ̂悤�Ɉ�̂��낤���B
|
�Q�@�\�z����B
�E�@�l�R�[�X����̎����ɂ͗\�z������B
�E�@���R�[�X����̎����ɂ͊��K���e��U��Ԃ点��B
�R�@���ׂ�C���ʂ��B
�@�@�ώ@�̕��@��m��B
�@�@�E�@��U�������C���̌������ŁC�̗����Ă���̓����̈Ⴄ���܂����݂�B
�@�@�E�@���̗l�q���L�^����B
�@�A�@�ώ@����B
�@�@���@�Y�Ǝ��̂��炾�̈Ⴂ�́H
�@�@���@���܂��̒��̕ω��̗l�q�́H
�@�@���@�z�����Ă���̃��_�J�̗l�q�́H
�S�@���ʂ����Ƃɂ܂Ƃ߂�B
|
�@���ɂ͗Y�E��������C���܂ꂽ���܂��͓������ɂ�ĕω����C�₪�ď����ɂȂ�B������������̃��_�J�̂͂�ɂ́C���炭�߂������߂̉h�{�̓������ӂ��낪����B
|
|
|
��̓��̎q�ǂ��̐����̗l�q�ׂ�B
�i�I���w�K�u�l�̂��傤�v�̓��e�j
|
�P�@�����̉ۑ��m��B
�@ �E�@
���e�X�g��]���e�X�g����ɁC������������Ȃ��_��C�l�̒a���ɂ��Ēm�肽�����Ƃ��e���ɂ��܂���B
|
�@�l�́C��e�̎q�{�̒��ŁC���܂�����Ԃ����ɂȂ�܂ŁC�ǂ̂悤�Ɉ�̂��낤���B
|
�Q�@�\�z����B
�@�E�@���R�[�X����̎����ɂ͗\�z������B
�@�E�@�l�R�[�X����̎����ɂ͊��K���e���ӂ�
�@�@�����点��B
�R�@���ׂ�C���ʂ��B
�@�@�@�ώ@�̕��@��m��B
�@�@�E�@���������Ƃɒ��ׂ�B
�@�@�E�@�r�f�I�Œ��ׂ�B
�@�A�@�ώ@����B
�@�@���@��̓��ł̐����̉ߒ��́H
�@�@���@�ւ��̂��ƑٔՂ̊����́H
�S�@���ʂ����Ƃɂ܂Ƃ߂�B
|
�@�l�́C�������܂�����̓��ŏ������������Ă���C���܂��B�ւ��̂��͑ٔՂƂȂ����Ă���C�q�ǂ��͂ւ��̂���ʂ��ĕ�e����h�{���Ȃǂ�������C����Ȃ��Ȃ������̂�Ԃ��Ă���B
|
|
|
���@�@�l�i�����Ȃǁj
|
|
���@���̒a���R�[�X�����Łu��������i��[�I�w�K�j�v����]���������C�l�̒a���R�[�X�����Łu�`�������W�i���W�I�w�K�j�v����]�����������Ώ�
���@���_�J�@���@��U�������܂��͎��̌�����
���@���v�M�@���@�������p�������u�@���@���_�J�̗��@�@�����[�N�V�[�g
|
���@�l�̒a���R�[�X�����Łu��������i��[�I�w�K�j�v����]���������C���̒a���R�[�X�����Łu�`�������W�i���W�I�w�K�j�v����]�����������Ώ�
���@�����i�Q�l�}���E�u�s�q���j
���@���[�N�V�[�g
|
|
�@�@�@�@�@�@�@���@�w���҂Q���ŕ�[�E���W�I�Ȋw�K���w������ۂ̓W�J��
|
|
|
|
|
�R�@���[�N�V�[�g�̊��p
(1)�@���R�[�X�i��������j�E�l�R�[�X�i�`�������W�j
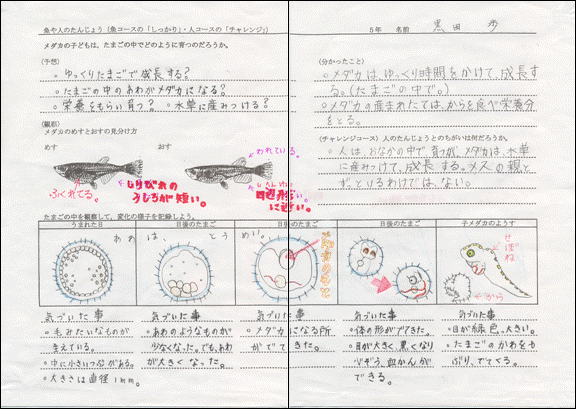
�@(2)�@�l�R�[�X�i��������j�E���R�[�X�i�`�������W�j
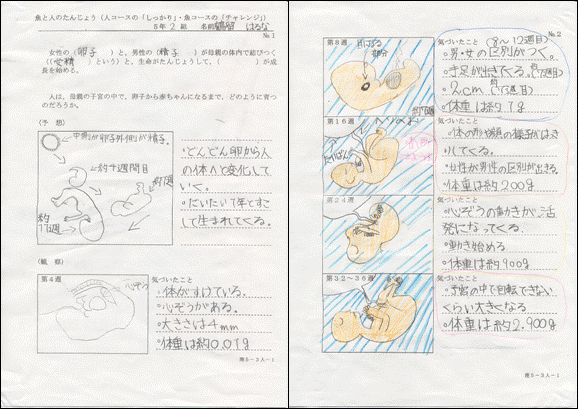
�@�u��������R�[�X�v�͊��K�����̕��K�I���e�ł���C�u�`�������W�R�[�X�v�͒��w�K�𒆐S�Ƃ������W�I�ȓ��e�ł���B�����̃��[�N�V�[�g�ɂ��ẮC���Ȋw�K�̌f���R�[�i�[�Ɍf�����āC���̎����֏Љ�C�ӗ~�t�����s���Ă���B
�S�@�]���K����̊��p
�@�@�ɉ������w�����[�����C��b�E��{���m���ɏK�������邽�߂ɂ́C�����̊w�K��c�����w���̉��P��}�邱�Ƃ��d�v�ł���B�����ŁC�u�]���K���v���쐬���C������l��l���m���Ɍ����C�w���ɐ������悤�ɂ���B�]���K����́C�e���ȁi�e�P���j�̕]���K���ƕ]���⏕�����̉����������̂ł���B�S�C�Ǝw���@���P�W������������ĕ]�����C�������݂��Ɋ��p���邱�ƂŁC������l��l�ɉ��������ߍׂ����w�����s���C��b�E��{�����̒蒅��}��B
�@(1)�@�S�C���s�����]��
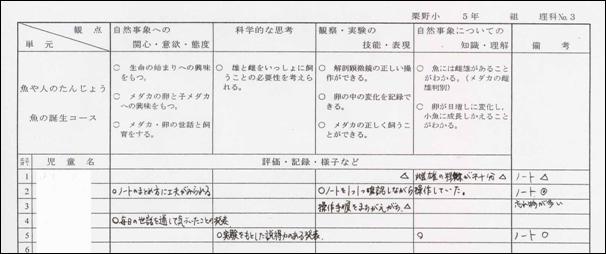
(2)�@�w���@���P�W���s�����]��
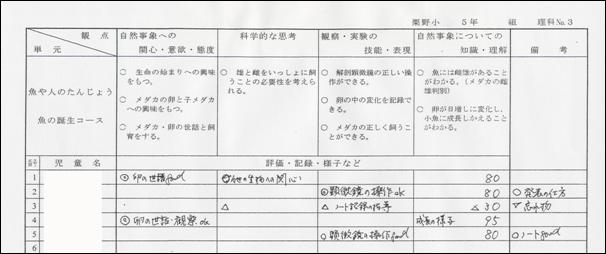
�@�S�C�Ǝw���@���P�W�̂��ꂼ��̕]�������p���邱�ƂŁC������l��l�ւ̕]�������ߍׂ����s���B��������ɁC���̋�̓I�Ȏw���ɐ������B
�T�@�����̐��ʂƉۑ�
(1)�@��[�E���W�I�w�K�̎w���W�J�Ăƃ��[�N�V�[�g��N�Ԏw���v��Ɉʒu�t�������Ƃɂ��C��̓I�Ȏ��H�ɂȂ��邱�Ƃ��ł����B
(2)�@�s�s�`���̎��Ƃɂ��C������l��l�ւ̑Ή����[�����C�����C�ώ@�̍ۂ݂̌��̖�������������ł���悤�ɂȂ����B
(3)�@�S�C�Ǝw���@���P�W�̓�l�ŕ]���K�����p���ĕ]�����s�Ȃ������Ƃ���C���������ׂ����]���ł��C��̓I�Ȏw���ɂ܂ō��߂邱�Ƃ��ł����B
(4)�@�����w�K���J��Ԃ������������u��������R�[�X�v�ł́C�����̎��Ԃ�w�����e�ɉ����āC�w�K�̗����ς�������e���œ_�������肷��Ȃǂ̍H�v���K�v�ł���B
(5)�@�S�C�Ǝw���@���P�W�Ƃ̎��O�̑ł����킹���C�X�ɏ[�������Ă����K�v������B
(6)�@�R�[�X�ʊw�K���s�Ȃ��ۂ̏ꏊ�̊m�ہC�����C�ώ@�̋��ދ���̏[����}��K�v������B
�N�������I�쏬�w�Z�@�@���@�@�@�J���@�P�Y
|