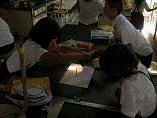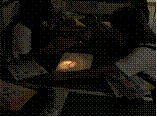|
単元名 |
3年 日なたと日陰をくらべよう | |||
|
単元のねらい |
1 日なたと日陰の地面の様子に興味をもち,日光が当たっている地面と当たっていない地面の様子を比べながら,日なたと日陰の様子には違いがあることが分かる。 2 かげの位置の変化と太陽の動きとの関係を調べることを通して,かげの位置は太陽の動きによって変化することが分かる。 | |||
|
学習の活動 (児童の素朴な見方や考え方) |
教師の支援・対応 (納得・実感させるために必要な観察,実験) | |||
|
1 かげ踏み遊びをしたり,陰で休んだ りして,日なたと日陰について問題意識をもつ。
・ どこに逃げればいいかな? ・ ここに逃げるとかげをふまれないぞ。 ・ 午後は同じ場所に逃げると捕まってしまうぞ。 ・ 走り回ったから,涼しい日陰で休みたい。 ・ 日陰は地面が冷たくじめじめしていて,日なたは地面が温かく,からからしているな。
2 かげ踏み遊びの体験をもとに,調べ たいことを決める。
・ かげの動き方について調べたい。 ・ 地面の日なたと日陰の温度の違いを調べたい。 3 日なたと日陰の地面の温度やかげのできかたについて調べる。 (1) 午前10時と正午の2回,日なた と日陰の地面の温度を調べる。 ・ 午前10時は日なた,日陰はあまり変わらないね。 ・ 正午は日なたの方は大きく温度が上がっているよ。日陰の温度は少ししか上がっていないね。 (2) 午前11時頃と20分後の2回,かげの動き方を調べる。 ・ 20分ぐらいしか経っていないけど,かげが動いたよ。 ・ かげの動きは太陽の動きと関係しているのかな。 (3) 遮光プレートを使って,太陽が動いているか調べる。 ・ 太陽は東から西へ動いているよ。 ・ かげの動きと太陽の動きは反対みたいだな。 (4) 観察用具を作り,朝・昼・夕方にかげがどう動くか。また,太陽はどう動くか遮光プレートを使って調べる。 ・ 太陽と反対方向にかげができているよ。 ・ 朝と夕方は昼に比べてかげが長いね。 ・ 太陽とかげはだいたい同じ時間に同じ長さだけ動いているね。
(5) かげはなぜ朝と夕方に長く,昼は短いのか懐中電灯を使って調べる。 ・ 懐中電灯(日光)の高さが高いと かげは短くなり,低いとかげは長く なるよ。
4 日なたと日陰の地面の温度やかげのできかたについてまとめる。 ・ 日なたの地面の温度は日陰よりも高くなる。 ・ 日なたの地面が温かいのは日光であたためられたからである。 ・ 太陽は東から南を通り西に沈む。 ・ かげの向きは太陽と反対の方向にできる。 |
○ 木等の陰の当たらないところに遊びの場を設定し,午前と午後の2回,かげ踏み遊びをする。
○ 午後のかげ踏み遊びの後,休憩を取るように指導する。その際,日陰に児童は移動するので理由を考えさせ,日陰と日なたの地面を手でさわり,違いに気づかせるようにする。
○ 前時の体験を想起させながら,どんなことを調べたいか,できるだけ児童の言葉で発表させる。 ○ 思い浮かばない児童がいた場合は,前時の様子の写真を提示し,どんな疑問があるか考えるよう助言する。 ○ 教科書を参考に,温度計の見方や使い方,地面の温度の測り方をしっかり理解させておく。 ○ なぜ日なたの方が温度差が大きいのか,日光が地面に当たると地面の温度が上がることを生活経験等と関連付けながら理解させるようにする。
○ グループごとに棒を立て,時間が経った後のかげの動きを調べさせる。 ○ かげは東に動くことから,なぜ動いたのかを考えさせる。
○ 動きが分かりやすいように,建物との境目などで見るよう助言する。
○ 前時の学習をもとに「では,かげは朝どちらにあっただろう。また,太陽はどの方角にあるのだろう」と投げ掛け,児童が問題意識をもって観察できるようにする。
○ 方位磁針で方角をきちんとあわせる。 ○ 記録した線と同じようなかげになるよう懐中電灯を動かす。 ○ 普段見る太陽と,懐中電灯の動きを重ね合わせながら,かげのでき方を理解させる。
○ 自分の記録や教科書のまとめを見ながらまとめさせる。 ○ 単元のプリントを行い,習熟を図る。 | |||
|
(成果と課題) ○ かげ踏み遊びをしたり,温度計や観察道具を使って学習したりすることを通して,児童は結果を基に,調べて分かったことを自分なりにまとめることができた。 ○ 棒とガラスと比較し,日光を遮るものがあるとかげはできることを指導したが,「なぜ,かげはできるのか」という理由の定着は十分図ることができなかった。 | ||||
|
(霧島市立小野小学校 教諭 草留 哲也) | ||||