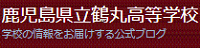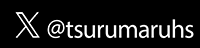公開日 2016年09月09日
由来
校名の由来
校名の「鶴丸」は、旧藩主島津氏の「鶴丸城」に由来し、 藩学の伝統を後世に伝えるとともに
平和と穏健を象徴するものである。
この校名が名乗られたのは、旧制鹿児島県立第一中学校と旧制鹿児島県立第一高等女学校とが
統合され、新制高等学校となった昭和24年4月からである。
校章の由来
丸い地球に大きく羽ばたく若鶴を配して
若人の夢と理想 世界に雄飛せんとする意気 を象徴する

理念
建学の理念
好学愛知
自律敬愛
質実剛健
教育目標
憲法・教育基本法の精神及び建学の理念に基づき、個性を啓発して人格の完成を目指し、
国家社会の繁栄と国際社会の進展に貢献し得る有為な人材を育成する。
学問を愛し、誠実にして敬愛の精神に富み、気魄に満ちた高邁なる学徒の育成を有し、
醇乎たる校風の発展を期する。
教育方針
①基礎的・基本的な学力を培うとともに、自主的・積極的な学習態度を体得させ、
豊かな創造力の育成に努める。
②豊かな情操と教養を養い、人権を尊重するとともに、調和のとれた人間性の育成に努める。
③心身を鍛錬し、たくましい気力、体力の育成に努める。
生活規範
この生活規範は、昭和41年「生活規範第12条」(ミニマム・エッセンシャルズ)として制定され、鶴丸生の日常生活、学習活動の基盤として継承されてきているものである。誠実にして品位ある学徒を目指し、未来のよき家庭人・社会人を目指して、この12箇条を実践躬行してほしい。
「玉みがかざれば光なし。才能の有る無しは、一生かかって勉強してみなければわかるものではありません。イクラヤッタッテオレハダメナンダ、などとあきらめてしまわないで一ぺんに無理をせず、地道にこつこつと、日々規則正しく、精いっぱい勉強することが肝心です。」(天野貞祐)
①万事質実剛健を旨として生活し、身のまわりのことはすべて自分の手できちんと整理整頓すること。
②服装規定をよく守り、いささかの乱れも見せないこと。
③朝は早目に起床し、朝食をしっかりとしたため、始業10分前までに登校しておくこと。遅刻、欠課、早退および夜間外出は絶対に禁物。
④授業と教科書が何よりも大事。天与の資質は人によって違うのだから、席次を気にする必要はない。それぞれ自分なりに、授業や教科書の大綱を押さえ本義を消化することに精いっぱい努めればそれでいい。宅習は最低4時間、うまずたゆまず行うこと。テレビをはじめ通俗的な娯楽に心を寄せるな。
⑤からだがなまらないように、日々適度の運動をすること。公共物を大切にする習慣を身につけるためにも、校舎内外の清掃は全員力を合わせてとことんまでやること。
⑥栄養摂取を心がけ、偏食に陥らないように気をつけること。「ニンジンはきらいだ。」「魚は好かない。」などとは不心得もはなはだしい。
⑦つねづね精神衛生に注意し、「かねて気象をもって己に克ち居れよ」と言われた西郷南洲翁の遺訓に従い、意志力の鍛錬につとめること。
⑧夕食後、家族の人たちと団らんのひとときを持ち、その日学校であったことを簡潔に話したり、弟妹の言うことを静かに聞いてあげたりすること。お互いに話題のないときは合唱したまえ。
⑨朝夕のあいさつはもちろん、「どうぞ」「ありがとう」「すみません」などの言葉を機会をとらえては、誰に対しても、はっきりと口に出して使うこと。他人の好意に接しながら「ありがとう」というたった一言が口をついて出ないようでは、君の精神はすでにむしばまれているものと反省したまえ。
⑩敬天愛人。自他共存。自己中心でだけものを考える幼児性から一日も早く抜け出し、人間らしい人間となるべく、機会あるごとに他の人々のためにつくす「フォア・アザーズ」の精神で事態を処理するようにつとめること。
⑪感情のたかぶりやいらだちを可能な限り抑えるように努力し、紳士淑女をめざして寛容な徳を積み重ねていくこと。暴力をふるうなどは、理由を問わず、いかなる場合でも言語道断。
⑫三年間のうちに、数は少なくてもいいから、生涯かけて喜びも悲しみも共にし得る親友をつくること。そのためには、友人同士心の底から敬愛し合い、やがて家族ぐるみのつきあいまでもってゆくことが必要である。わるふざけをしたり、相手の心身の欠点をあげつらったりしてはいけないことは、言うまでもない。