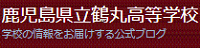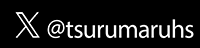最終更新日 2026年01月28日
目次
全校朝会7(令和8年1月26日)
今日は,3年生にとっては最後の全校朝会です。最後なので,せっかくなら3学年そろって体育館で実施しようかとも考えたのですが,先週からかなり寒い日が続いてましたので,今日は各教室でお話を聴いてもらうことにしました。3年生最後の全校朝会に何を話そうかいろいろと迷ったんですけど,3年生は3月の末までに全員,成人年齢である18歳を迎え,4月からは鶴丸高校とは別の場所で,中には一人暮らしで新しい生活を始める人も出てきます。いよいよ社会との接点が開かれていく大事な時期になってきます。
そこで,今日は3年生が卒業して社会に出て行くにあたって,(参考になるかどうかわかりませんが,)私自身が「社会人として仕事をする上で大切にしていること」というお話をしてみたいと思います。1年生,2年生も是非一緒に聞いてください。
私は公立学校の教職員として働いています。若い頃には教諭として学級担任の仕事をしたり部活動の顧問をしたりという仕事をしていましたが,今は「校長」職についています。よく「校長先生ってどんなお仕事をされてるんですか?」と聞かれますが,わかりやすいのが,今このように,皆さんにお話をしたり,職員会議等では先生方に話をしたり,又は学校の外に出て,例えば鶴丸高校の校長だと県の高校野球連盟の会長に割り当てられたりしますので夏の甲子園の県予選大会の時に挨拶をしたりというように「人前に出て話をする」「挨拶」をするというお仕事,これが結構たくさんあります。でも,それは校長の仕事のほんの一側面にしか過ぎなくて,正式にいうと,本来の「校長の職務」というのは実は法律に定められていて,そこに明記されているのです。
では,【2ページ目】を見てください。
「学校教育法」という法律なんですが,そこには,校長の仕事とは「校務をつかさどり,所属職員を監督する」と書かれています。「校務をつかさどる」というのが,少し抽象的でわかりにくいのですが,法律というものには,その下に「施行令とか施行規則」というのがあって,その中に,より具体的な内容が書かれてあるんです。
2ページ目の真ん中にありますが,そこには,例えば教育課程(これは鶴丸高校では,数学の時間を週に何時間やりましょう,とか,こんな教科書を使ってやりましょうという教育内容)の決定ですとか,これだけのお金をこんな事やこんな物に使いましょうという予算の執行であったりとか,コロナやインフルエンザが蔓延する恐れがある場合は学級閉鎖や臨時休校をしましょうかとか,また,高校の校長の場合は進級,卒業の認定や入学の許可などといったものが,校長の職務としていろいろと具体的に定められています。
これらの決定は私が口で「やりましょう」と言っただけでは成立しません。当然,これは正式な文書にサインをしたり印鑑を押すことで完結しますので,実は私の一日の大半の時間は,毎日大量の文書に目を通して,その内容を理解して印鑑をひたすら押すという仕事に大きな時間を取られています。
文書を読むだけで,すぐに判断してハンコを押せるものもありますが,慎重な判断が必要なものは,担当の先生からの説明を受けたり,私の方から質問や聞き取りをして,判断していきます。
また,いろいろな学校行事の企画立案,そしてその実施等については何から何まで一人でやるというのは無理ですので,担当の係の先生方に案を作ってもらって,その上で職員会議などを開いて広く先生方の意見を聞き,最後は,「これで行きましょう」とか「これでお願いします。」という決定を行います。ですから,私の仕事の大半は,毎日何かを「判断,決断している」というわけです。
この,「判断し決断する」ということは,私は「校長」という立場だからそういう場面は特に多いんですが,皆さんもこれから社会出れば,親や先生も助けも借りずに,自分自身だけの判断や決断で行動しなければならなくなります。そして,それは年齢を重ねれば重ねるほど,おそらくそういう場面が徐々に多くなってくるのだろうと思います。というわけで,
私がその判断や決断をする際に心がけていること,これをお話ししてみたいと思います。
まず,一番に心がけているのは,私の場合,学校という場,教育という場で仕事をしているわけですから,その判断や決断が,教育の目的・教育の目標・こどもの命を守る・・・といった,根本的な「教育の理念」とすべきものに叶うものなのか?ということをいつも考えてみるようにしています。何か物事を判断をするときに自分自身が「拠って立つところ」は何なのか,そして行動するときに自分が一番大切にしている事は何なのかという自分自身の「行動原理」というのか自分の「原点」みたいなもの,こういうものに立ち帰って考えてみることが大切だと思っています。
ちなみに,「教育の目的」というのはしっかりと法律で定義づけられいて,3ページの下の方です。教育の目的って,一義的には個人個人の「人格の完成」なんです。でもそれだけではなくて,その個人個人が「社会の形成者」となることも求められています。
この「社会性」身につけるという部分は,特に今の時代の「学校」に求められる大変重要なものだと思っています。
では,次に【4ページ目】を見てください。
私が判断や決断をする際に心がけていることの2番目は,「それが法的な根拠に基づいているか?」ということです。
日本は法治国家ですから,法律にはどう書いているのか,とか,また,それに準ずるような国や県の文書にはどう書いてあるのか,とか,そういうことをしっかりと理解し,それを遵守するということは極めて重要なことだと思います。最近は学校の指導を巡る裁判とか訴訟の事例も多く,その際「法律にはこのように書いてありましたが,学校としてその責務をしっかりと果たせたのですか?」と問われることも多いのです。
例えば,今年の4月から自転車通学生に対して学校としてヘルメットの着用を求めることとしました。おしゃれに気を遣う年頃の高校生の皆さんに思うところはいろいろとあったかと思うんですけれども・・・,この判断をしたのは,下の方に書いてありますが,道路交通法という法律が改正されて令和5年4月からヘルメット着用がしっかりとその法律に明記されたということが大きかったんですね。さらに,その右側にも書いてありますが,学校保健安全法という別の法律にも学校には登下校の際の安全指導の責務というものが明記されています。登下校時の安全ということで言えば,5年前に本校に近い場所で高校生の大きな自転車の事故も起こってますからね。法律論からいってもですが,最初の話の「こどもの命を守る」という学校教育の「原点」に照らしても,やはり,学校として,皆さんにヘルメットを着用してもらうという判断をさせてもらったわけです。
判断・決断するときにもう一つ私が心がけていることは多様な情報や意見を踏まえるということです。
ヘルメットの件では,生徒会をとおしてアンケートを取って皆さんの意識も確認しました。「着用は大事」という意見が過半数を超えたことも判断の材料の一つになりましたし,県内の他の学校の様子ですとか,他の都道府県,九州で言うと福岡県や大分県は県内の全ての高校でヘルメットを義務しているという流れもありましたので,これらの状況も判断の後押しにもなりました。
数字的なデータに加え,時代の流れとか世の中の雰囲気といった観点なども大事です。判断材料はやはり多ければ多い方がいいのだろうと思います。
これまでの説明とは逆の順番になりますが,これから社会に向かって羽ばたいていく鶴丸高校生の皆さんに,判断・決断をする場面で意識してほしいことです。
1つ目はいろいろな情報や意見にあたっておくことです。当然,本をたくさん読んだりすることなどに加え,情報をたくさん収集するためのツールですとか,また,それらを効率的にまとめるAIなどの使い方にも通じておく必要がありそうです。さらにいろいろな情報を正しく理解するためのスキルを向上するとか,そういうの意味での学校とは違った勉強も必要になってくるのかなと思います。
2つ目は(リーガルマインドと書きましたが)法的思考を持つこと。今の世の中はコンプライアンスに大変厳しい,コンプライアンスに敏感な世の中になってきているということは十分おわかりだと思います。そういう意味での「法的思考」=これは法律を守る,法律を知っているということだけでなく,物事を多面的に捉え論理性を持って考え,公正に判断といったような姿勢です。こういう姿勢がこれからもっともっと求められる時代になっていくと思います。
最後に3つ目は,やはりこれが一番かなと思いますが,判断に迷うときこそ(ほど)「原点」に立ち帰ること!私にとっては,先ほど言ったように「そもそも教育ってどんな仕事だったっけ?」ということに立ち返ります。皆さんも,社会に出て自分自身の判断で行動を行うときに,それぞれ一人一人が,自分の行動を支える「自分が拠って立つ所」とか,「自分の原点」だとか,「ブレない自分の軸」だとか・・・そういったものをしっかりと確立してほしいなあ,と思います。
多様な価値観があふれ,社会が大きく変動している時代だからこそ,しっかりとした自分をもってください。ということなんですね。
最後の【7ページ目】を見てください。
3年生は最後の全校朝会となりました。先週,大学入学共通テストを終えて,いよいよ今週あたりから私立大学入試が本格化します。そして2月25日に国公立大学の個別学力試験・2次試験が控えています。
大学入学共通テストはマーク式のテスト。大量の文章や資料を読んで短時間で処理をするという頭の使い方をしていましたが,2次試験は短時間に処理をするだけでなく「自分の頭の中で再構成して答案に表現する」力が問われます。皆さんが3年間頑張ってきた学習の真価がもっとも問われる,最後にして最大の場面というのがこの2次試験です。みなさんが時間をかけて頑張ってきた成果やその思いや気持ちを込めて,答案というよりも「一つの作品」を作り上げてほしい。その作品を採点者に評価してもらう,そんな気持ちで頑張ってきてほしいと思います。あと1ヶ月ですが,1ヶ月の時間があれば人間,結構なことができます。悔いのないように頑張って全力を出し切ってください。
共通テストの前後から緊張が続き,体力的にもですが,精神的にきつい日が続いていますよね。特に精神的な面は,周りはなかなかどうすることもできなくて,自分自身がそれを克服するしかありません。でも,それを克服できた時に,人は必ず成長します。
共通テストが終了した時,3年生の皆さんは,どんな気持ちがしましたか?(テストの出来,不出来という問題は別にして),とにかく全力を出し切って本気で頑張った経験をすると,「少し自分が成長したなあと」と感じた人も多かったのではないでしょうか?
2次試験が終わったらもっともっと強くそう思うはずです。一生懸命に努力してやりきった人は,その後に必ず何かを掴むはずです。この経験が皆さんをもっともっと大きくすると思います。よりよく成長できるよう,あと1ヶ月間,頑張ってください。
では,3年生77期生の皆さんの健闘を心からお祈りしまして今日の全校朝会の講話とします。以上でおわります。
全校朝会6(令和7年12月01日)
さて,この写真(スライド2)ここは「薩摩藩英国留学生記念館」。大きな建物ではないですが,いわゆる1865年に薩摩藩がイギリスに送り出した留学生たちとそれに関わるお話がよくわかるようになっている展示館です。
いちき串木野市の羽島というところにあるんです。「薩摩藩英国留学生=薩摩スチューデント」はこの地を出発してイギリスに行ったんです。
「薩摩スチューデント」は知ってますよね?
こちら(スライド3)は,おなじみ鹿児島中央駅前にある若き薩摩の群像です。いわゆる「薩摩スチューデント」たちの像ですよね。
今日のお話したい人物は,薩摩スチューデントの中でもこの人。像の北側から見たときにこの真ん中の椅子に座っている人物,「寺島宗則」のお話です。顔の表情など落ち着いた感じがしますが,彼は当時30代,団長の新納久脩と同じ年,寺島や有名な五代友厚などは留学生というよりも留学生の引率役,薩摩藩の使節として参加しています。
(スライド4)にあるように寺島は1832年に鹿児島県阿久根市に生まれます。
当初は叔父の蘭方医松木宗保の養子となり「松木公安」を名乗っています。7歳頃に長崎に蘭学の勉強へ,そして14歳の頃には江戸に出て勉強。20代の頃には父の後を継ぎ医者に,しかも当時の薩摩藩主島津斉彬の侍医とななったんです。優秀だったんでしょうね。(スライド5)
西郷隆盛や大久保利通もその薫陶を受けた名君の誉れ高い島津斉彬公の侍医ということですから,ある意味,西郷や大久保以上に斉彬と関係が深かったかもしれませんね。斉彬は今の仙巌園で尚古集成館をつくり造船事業,反射炉・溶鉱炉の建設,地雷・ガラス・ガス灯・写真・電信の製造などを行っています。寺島は後に「斉彬公は脳みそが二つあった」と言っています。私は寺島こそスーパーマンだと思っているのですが,その寺島をして,斉彬公は天才的だと言わしめているので島津斉彬公は本当にすごい人だったんだろうと思います。照國神社の横に探勝園という公園がありますが,そこで,斉彬公に命ぜられた寺島が,電気通信の実験をおこなった跡が史跡として残っています。是非見に行ってみてください。
1861年29歳の時には,医師であるということそして優れた語学力が買われて幕府のヨーロッパ派遣使節に選ばれ翌1862年に洋行。それまで日本の外国語と言えばオランダ語でしたが,寺島はこれからはオランダ語ではなく英語だと感じていたらしく,すでに英語の勉強を始めていたらしいですが,このヨーロッパ使節の経験で,さらに寺島の英語力は上がっていったと言われています。この幕府のヨーロッパ派遣使節は総勢38名の使節団で文久遣欧使節と呼ばれますが,一緒に行った人に福沢諭吉がいます。
さて,寺島がヨーロッパから行って帰ってくる1862年に,薩摩藩の島津久光の行列に遭遇したイギリス人が殺傷される生麦事件が起こってます。当然,その翌63年に薩英戦争が起こるわけですね。
帰国後,薩摩藩で,船奉行をしていた寺島はイギリス軍に捕らわれてしまいます。一緒に捕らわれたのが,五代友厚です。この二人,間近でイギリス軍の様子を見て攘夷の難しさを知り,イギリスとのパイプもできるわけですが,捕虜になったことで薩摩藩や幕府からはスパイの容疑をかけられ一時期追われる身となります。この時期から松木公安という名ではなく寺島宗則を名乗るようになったと言われます。
五代友厚は本当に才覚がある人ですが,この時は寺島と一緒に捕まった五代友厚が機転を利かせます。薩摩藩にお詫びを入れるとともにこう進言するんですね。「武力でイギリスを倒すのは難しいとわかりましたよね」と,「逆にイギリスのいい点を学んで薩摩藩の国力を増し,幕府に変わり薩摩藩など力のある藩で政権を担当すべきだ」と,「そのために薩摩の若い者をイギリスに派遣しましょう。私たちなら話がつけられます・・・」と言うわけです。これが薩摩スチューデントです。さっきも言いましたが,五代と寺島は留学生ではなく,実質,この提唱者で引率者なんですね。
イギリスに渡った寺島は,得意の語学力を生かしてイギリスの主要な人々に日本の政情を説いていきます。「今徳川幕府に力はありません」「私たち有力な藩の連合体が徳川幕府に変わり天皇を中心とした新政府を樹立しようと思っています。」「イギリスの力を貸してほしい・・・」このときの寺島の働きは大きかったと思いますよ。
イギリスから戻ってきた寺島は時の薩摩藩主島津忠義に,土地と人民を天皇に返すということを藩主に提言している。いわゆる版籍奉還なんですが,明治新政府が正式に版籍奉還を各藩に呼びかけるのはその2年後なのですが,これを寺島は早々と実現しようとしたんですね。
(スライド6)さて,1868年は日本史においては明治元年。明治の新政府が樹立されます。新政府で寺島が任されたのは神奈川県の知事です。中央政界から離れた感じもしますが,神奈川には横浜があります。外国の外国人居留地・領事館は横浜に集まっていますから外交のプロである寺島にはうってつけの役目だったと思います。
この横浜時代に,寺島がやったことが,日本の近代化において非常に大きな意味を持ちます。それが電信線の架設です。
寺島は政府の許可を得て,1869年に横浜の役所と裁判所の間に電信回線を敷設し通信実験を成功させます。成功を確認すると寺島は同年中に,横浜・東京間での電信による電報の取り扱い事業を開始します。
その後,政府は通信線の建設を急ピッチで進め,わずか5年で北海道から九州までを結ぶ列島横断ルートが完成しました。当時を考えれば,このスピードは驚異的な速さだったと言えます。
世界の列強各国は日本の通信権を虎視眈々と狙っていました。最新の通信インフラである電信の設置を他国に任せてしまえば,国の中枢を握られたも同然であり,植民地にもなりかねない話なのです。寺島は国内の電信網を速やかに国営で完成させることで外国による国内電気事業への介入を防ぎ,通信における主権を確保しようとしたわけです。
寺島は,寺島自身も自分は外交が得意で最後は自分は外交官だという意識があったと思いますが,寺島はこの功績により寺島の代名詞としては「外交の父」ではなく「電信の父」「電気通信の父」と呼ばれることが多いんですよね。
1873年は明治の政治でも非常に大事な年,いわゆる明治6年の政変ですよね。征韓論の件などで西郷隆盛などが鹿児島に帰ってしまいます。残った大久保が頼りにしたのがこの寺島です。寺島は,いよいよ明治政府の主要メンバーである参議となります。そして,参議と兼ねてライフワークである外交の仕事を取り仕切る外務卿(今の外務大臣)を6年間務めることになります。
寺島の最後の大仕事となったのが不平等条約改正交渉。これは日本史選択者の人たちはよくわかっているかと思いますが,粘り強い交渉で,アメリカとの間では関税自主権回復に成功しそうになるのですが,最後は英国等の反対で実施に至りませんでした。しかし寺島などのこの努力が後の条約改正につながっていくことになります。
1879年には6年努めた外務大臣から文部卿になっています。この人,今でいう文部科学大臣も務めたのですよ。
私の寺島宗則愛を叫ばしたら1時間あっても足りないかもしれません。地元鹿児島の人間としてひいき目に見ているのかしれませんが,私はもっともっと評価されるべき人物だと思っています。個人的には大河ドラマにしてほしいと思ってるくらいです。(スライド7)
好奇心旺盛で開明的だし,柔軟性や先見の明があるし,決断力・判断力・実行力あり,打たれ強いし,粘り強い・・・。
(スライド8)さて,今日の全校朝会のテーマは「グリット」と言う言葉でした。このグリットという言葉,よくビジネスシーンなどで使われていましたが,最近は教育の分野でもよく耳にします。私はこの寺島宗則こそ高い「グリット力」のある人物なのではないかと思うのです。
この言葉,世界有数のコンサルティング会社やニューヨークの公立中学等で勤務をしたこともあるというペンシルベニア大学心理学教授のアンジェラ・リー・ダックワースという人が唱えた言葉らしいです。
アンジェラ・ダックワース教授は,成績が優秀な学生や社会的に成功した人の共通した特徴を研究し,「社会的成功は才能やIQよりも「粘り強さ」,すなわち「やり抜く力(GRIT)」が重要である』というグリット理論を提唱し世界的に注目を集めました。
辞書を引くとGRITだけでも「勇気」「気概」「闘志」という意味があるようなのですが,最近は,このスライド書いてあるようにGRITのそれぞれの頭文字をとって,ガッツ,レジリエンス,イニシアチブ,テナシテイィの4つで整理されているようです。2番目のレジリエンス=回復力・復元力などは最近,特に注目されて研究も進んでいるようです。
ダックワースさんの本を読むと「やり抜く力」が大切だということに加え,やり抜く力に欠かせないのは「人生の目的と結びついた興味関心」=「情熱」だというのです。
多分,寺島宗則にとっての人生の目的って多分「この国が外国にひけをとらないようないい国にする」という「情熱」だったと思うのです。
皆さん,君たちの人生の目的ってなんですかね。3年生は,今,受験勉強でそれどころではないけれど,勉強の合間に少し考えてみてほしい。何のために受験勉強をやり抜こうとしてるんでしたっけ。大学でこんな研究をしてみたい。社会に出たらこんなことでこういうことで貢献してみたい。それぞれが頑張ろうとしている目的があるはずですよね。そんなことを本気で思ったときに「やり抜く力」はでてくるのかもしれません。
(スライド9)最後に,寺島宗則が育った阿久根の様子です。特に寺島が生まれた脇本というところは砂浜が,海がきれいで自然豊かなところです。今年日本人のノーベル賞が2人でましたが,ノーベル賞受賞者,出身大学は東大・京大等が多いものの高校の出身者で見ると地方の公立高校が多いということがニュースになっていました。若いときに地方で,寺島は鹿児島の中でもまた地方ですからね。美しい自然を見て,将来について,この国の世界の未来についてじっくりと落ち着いた気持ちで考えられる環境で育ったことは大きな意味をもっているのかもしれません。皆さん,(3年生は特に,)鹿児島で学んだ,鶴丸で学んだことに自信を持って頑張ってください。
○ 以上で,今日の校長講話を終わります。いよいよ12月に入ります。鶴丸生の皆さんの今後のさらなる活躍を心から願っています。
全校朝会5(令和7年10月27日)
皆さん,おはようございます。
今日は,今月11日に行われた文化祭について,文化祭当日は講評を行うことができませんでしたので,この場を借りて本校の今年度の文化祭とそれに関するについてお話をしたいと思います。
まず,生徒会の皆さん,特に文化局の皆さん,そして局長さんを中心に,本当に素晴らしい文化祭を企画・運営してくれてありがとうございました。開催前から周知・広報にも力を入れてくれていましたが,今年の文化祭の公式サイトは非常に完成度が高く,感心しました。サイトの制作には生徒会だけでなく,放送部なども協力してくれたと聞いています。
また,文化祭の係の先生方からは,当日,照明担当や会場整理担当の生徒が非常によく頑張ってくれたとの報告を受けています。これらの係は各クラスから選出されるため,必ずしも全員が希望して担当したわけではなかったかもしれません。それでも,与えられた役割をしっかりと果たしてくれたことを,とても嬉しく思います。本当にありがとうございました。
展示の講評については,文化祭当日はPTAの会長から学級展示についての講評がありましたので,今日,私からは,文化部の展示,特にの生物部の展示について少しお話したいと思います。
今回,生物部の展示を見に行った際,部員の方から「校長先生,よかったらこれを読んでください」と声をかけられ,この冊子をいただきました。『あこう』という木の名前がタイトルになっている,生物部の研究誌です。この研究誌は,生物部が創設された1962年に第1号が刊行され,1965年までの4年間発行されていたものの,その後は途絶えていたようです。今年度の部員の皆さんが頑張って,なんと60年ぶりに復刊してくれたとのことです。
この話を聞いて,私はとても嬉しく思いました。文化とは,先人から受け継いだ知恵や技術・技能を,今を生きる私たちが受け止め,昇華させて次の世代へと伝えていくものだと思います。その意味で,生物部の研究誌の復刊は「文化のリレー」が行われた象徴的な出来事であり,大変意義深いものです。このような意識を持って取り組んでくれた皆さんを,非常に頼もしく感じました。
最近ではデジタル化が進み,紙媒体が敬遠される傾向もありますが,形として残るものには,そこに込められた心が感じられるように思います。鶴丸高校の生物部の皆さんにとって,この研究誌は後輩たちが研究を進める上での道しるべとなるでしょうし,卒業後に高校生活を振り返る際にも,自分が何を思い,どんな気持ちで研究に取り組んでいたかを確認できる,非常に意味のあるものになると思います。
今回の文化祭は,生物部に限らず,各クラスや各部活動においても非常にレベルが高く,まさに鶴丸高校らしい,そして君たちらしい文化祭だったと思います。中心となって活躍してくれた1・2年生の皆さんは,これからも自信を持って学校生活を送ってください
さて,3年生にとっては,主役の座を1・2年生に譲っての初めての学校行事となりましたが,受験勉強の合間の良い気分転換になったのではないでしょうか。先生方も,3年生に向けてパフォーマンスを披露してくれましたが,いかがでしたか? 先生方の思いは,皆さんに「届いた」と信じています。多くの方々が,皆さんを応援しているのです。
共通テストまで,あと3か月ほどです。時間を無駄にせず,1日1日を大切にして,しっかりと頑張ってください。
以上で,今日の校長講話を終わります。今週末からは11月に入ります。鶴丸生の皆さんの今後のさらなる活躍を心から願っています。
令和7年度 後期 始業式(令和7年10月1日)
皆さん,おはようございます。今日の始業式講話もスクリーンを使いながらお話をしていきたいと思います。
前回,終業式のお話では,「For Others」に関するお話の中で,皆さんが将来大人になったときに,For Othersの精神で,世の中に,社会に貢献できる人間になれるよう「この高校時代にしっかりと準備をしておこう」「今,この鶴丸高校で頑張ろう」とお話をしたと思うんです。
今日は,世のため人のためにも,だけど,何より,皆さん一人一人が自分のためにも,今,この時,この高校生の時期を頑張っていこうというお話をします。
この秋休み,ちょっと唐突なお話で申し訳ないのですが,動物園に行ったんですよ。動物園の動物,皆さんは何が好きです?
私はサルが好きなんですよ。サルも人に近いサル,例えばチンパンジーやオランウータン,ゴリラといった類人猿です。かれらのジェスチャーとか見てるともう人間ですよね。見ていて飽きないです。彼らは,檻の向こうから見ている私たちの反応もみて動いていますよね。
さて,スライドにはゴリラの赤ちゃんの写真を出しましたが,「ゴリラの赤ちゃんは・・・」。 ・・・には,なんと続くと思いますか。
実は,私,今年の春先にゴリラをはじめとする霊長類・類人猿研究の第一人者として知られる総合地球環境学研究所の所長,山極壽一先生のお話を聞く機会があったんです。
山極先生は,アフリカ各地で野生ゴリラの社会生態学的研究に従事,その生態から人類の起源を探究している研究者です。実は本県屋久島で野生ニホンザルの調査にも携わられたご経験を持ちます。日本霊長類学会会長,国際霊長類学会会長,日本学術会議会長などを歴任されて,2020年までは京都大学の学長もお務めになられました。
私が5月に聞いた講演会は,私のような教育関係者が集まる会でしたから,先生はご自身のゴリラ研究をもとに人間の教育・子育てに関してお話をしてくださったんです。
で,先ほどのゴリラの赤ちゃんに戻ります。山極先生が人間の赤ちゃんとゴリラの赤ちゃんの違いの話から人間の子育てについてお話ししてれたのですが,その違いなんだかわかりますか? ゴリラの赤ちゃんは・・・・
「泣かない」んだそうですよ。
ゴリラの赤ちゃんは3~4年,チンパンジーは5年,オランウータンは7年ほど母乳を吸って育つ。常に母親にしがみついてほとんど泣かないんだそうです。これらの類人猿は森の中にすんでいます。私たち人類は,その進化の過程で森を捨てて広い世界に直立二足歩行で飛び出した生き物。
ゴリラの赤ちゃんは,腕の力が強くてお母さんから離れずに安全な状態,また,ある程度安全な森の中ですから泣く必要もなかったんでしょうね。
人間の赤ちゃんは1歳から1歳半で離乳します。これは人類は絶滅を避けるために,子供をたくさん産むために,お母さんが次の赤ちゃんを早く産めるためだといわれます。
人間の赤ちゃんは自力で母親につかまる力がありません。大きな声で泣くことで周囲にケアを求めます。早くに離乳する子どもを育てるには,母親だけでなく,共同体全体での保育が必要になりました。お父さんも赤ちゃんを抱っこする。おじいちゃんやおばあちゃんも抱っこする。人間はこの乳幼児期に,いろいろな他者の気持ちを感じ取る「共感力」を発達させることがてきると山極先生は述べています。人間の子育てにおいて特に重要なのはまずは,この乳幼児期だというんです。赤ちゃんが泣いたら反応,いいレスポンスをしてあげないといけない。これによって他の動物,類人猿とも異なる発達した「共感力」を身につけることができるのだそうです。
君たちは,ここを上手く通過してここにいるんだと思うんですよ。
そして,山極先生がおっしゃるに子育てにおいて次に大切なのが,「思春期」なんだそうです。
人間は霊長類の中でも特に,脳の発達を優先させるために身体の成長が遅いという特徴があります。生後1年で脳の大きさは誕生時の2倍になり,その後,サイズだけなら6歳=小学校に入る頃には,もう大人の脳の90~95%のサイズになっているといわれます。そして12~16歳頃に脳の大きさはほぼ完成します。
保健の授業等でも習ったともいますが,脳の成長がピークを迎える12~16歳頃に,身体の成長が急激に進みます。これが「思春期スパート」です。この時期には男性,女性のそれぞれ性ホルモンの分泌が活発になります。この性ホルモンの急激な増加は,身体的な変化(第二次性徴)だけでなく,心にも大きな影響を与えます。理由もなくイライラしたり,落ち込んだりするなど,精神的な不安定さを引き起こすことがあります。心身のバランスが崩れ,感情のコントロールが難しいんですね。
この時期に感情のコントロールが難しくなるもう一つの理由を挙げておきます。
脳は大きさ自体,思春期に完成しているといいましたが,その中身はまだまだなのです。脳内の神経細胞の発達やその結びつき,ネットワークはまだまだ「スカスカ」な状態。しかも,その発達は場所によって時間差があるのだそうです。
脳の中身,ど真ん中の方に「大脳辺縁系」というところがあります。ここは「感情や衝動」をつかさどるところなのですが,大脳辺縁系は,思春期に先行して急激に発達します。そのため,思春期に感情の起伏が激しくなったり,欲求や衝動が強まったりします。
一方で,「理性的な判断や感情のコントロール=思考を司る」を行うところは脳の前方にある「前頭葉(前頭前野)」というところです。前頭葉(前頭前野)は,大脳辺縁系よりも遅れて発達し,20代半ば,25歳頃まで成熟し続けます。
このように,感情の暴走を止める「ブレーキ役」である前頭葉(前頭前野)が未熟なため,感情や衝動が先行してしまい,行動の制御が難しくなる「ミスマッチ」の状態が生まれます。これが,思春期の向こう見ずな行動や不安定な感情の一因となります。
次のスライドは,先生の著書などから「思春期」についてまとめたものです。読んでみますね。思春期は,
単に身体が大人に近づくだけの時期ではなく,脳の成熟にともない,身体的にも精神的にも不安定になる中で,複雑な社会を生き抜くために不可欠な「社会性」や「適応力」を身につけるための最も重要な学びの時期。
- 社会的な環境の中で他者との関係性を調整し,自分自身のアイデンティティーを構築する時期。脳の大きさが完成した後も25歳頃までは他者の心の状態を理解し,文脈に応じて自分の中で解釈する能力を成長させる必要がある。現代社会がAIの発展などによって情報過多になり,人間の社会性が失われつつあることは不安。
- 思春期こそ「自分が出合った変化にどう対応したらいいのか」を自覚して学ぶ機会が必要。この時期に本などを通じて自分が経験していないことを学び,好奇心を鍛えるべし。
皆さんが生きている今のこの「思春期」の時期に,理性や思考をつかさどる前頭葉(前頭前野)をよりよく発達させることが大切なようです。いろいろと物の本を読むと,前頭葉(前頭前野)を発達させるためには,やはり「思考する」「考える」=「学ぶ」という行為が大切です。
暗記という行為は最近はネガティブに捉えられる嫌いもありますが,暗記を行うことも重要な脳のトレーニングのようです。書かれていること,言われていることについて相手が何を意図しているかを推察・洞察し,それを読解する,解釈する,そのような練習も大切。自分が意図していることを自分の頭の中で組みたてて相手に伝える,表現するという練習も大切なようです。いろいろなトレーニングを組み合わせて脳ミソに汗をかかせるというんでしょうか。そういうことを若いうちにすべきなのだと思います。
文系の皆さんは数学的な思考が苦手な人が多いかもしれませんが,物事を帰納的に考える,演繹的に考える。いろいろな角度から,いわば脳を逆立ちさせ,考えに考えるということも重要なようです。
大学とか大学院くらいの年代まで勉強するということには,エビデンスがあるんですね。前頭葉が発達する25歳くらいまではやはり人間は「学び」の時期なのです。
③の文章で「本などを通じて自分が経験していないことを学び,好奇心を鍛えるべし。」とありました。若い時期の「読書」も大切なんですね。あと,大学生になったらですが「旅行」などもいいと思いますね。若い人は未知の環境に何度か身を置くことで新たな気づきも多くなってくるように思います。
さて,今日は,文化人類学の観点から人が人として不可欠な「社会性」や「適応力」を身につけるためにも,そして,その後,50年も60年も続く長い人生を豊かにするためにも,今の君たちの年代から25歳くらいまでの時期は考える,学ぶ,勉強するのに最も重要な時期だというお話をさせていただきました。まあ,何かの誰かの台詞ではないですが,やっぱり,勉強やるなら,「いつやるの,今でしょ。」ということになるのでしょうかね。
以上で,令和7年度後期の始業式の講話を終わります。
それでは,皆さん,後期(2学期)も頑張りましょう。
関連記事
- 令和7年度 前期 式辞・挨拶等(2025年10月02日)