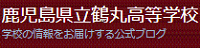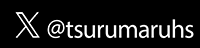最終更新日 2025年07月31日
全校朝会4(令和7年7月7日)
おはようございます。
今日は暑いということもありますが,各教室に固定型のプロジェクターも付きましたし,通信環境や端末等も整備されてきた中,教室間を結ぶリモート会議でのやり取りができるのか試してみたいということもありましたので,このような形(各教室でのリモート形式)での全校朝会にしてみました。
今日上手くいったら,夏場の学年での集会とか,生徒会の話し合いとか,クラス対抗でディベートとか,あとは,他の学校との交流とか国境を越えて海外との交流とか・・・いろいろと可能性が広がるかもしれません。皆さんもアイデアを出して積極的にICT機器を活用してもらえればと思います。
さて,今日は令和7年7月7日,7並びの縁起がよさそうな日です。鹿児島の場合は旧暦で関連行事を行うことが多いですが,全国的には今日が七夕の日ですので,少しロマンチックな話をしてみたいと思います。
まず,写真のこの花,なんていう名前の花か知っていますか。
「アガパンサス」という名前の花なんです。ちょうど今の時期,庭先や公園の植え込みなどでよく見かけます。水色の爽やかな感じの花ですね。
この「アガパンサス」,ギリシア語で「愛」という意味を持つ「agape(アガペー)」と「花」を表す「anthos(アンサス)」が合わさったと言われているので,つまりは「愛の花」って感じの名前の花なんでしょうね。
今日はこのお花にまつわるギリシア神話のお話をしてみます。
ギリシア神話ってもちろん古代ギリシアの神々のお話なんですけど,いろいろいる神様の中でも,宇宙や天候を司る全知全能の神で,神々の王とされる最高神にゼウスという神がいます。
で,このゼウスにヘラという奥さんがいるんですけど,このゼウスが,まあ,若い女性が大好き。これで困ったことになるんです。
この王妃ヘラに使える侍女にイリスという娘さんがいました。このイリスはヘラに使えて,神の言葉を人間に伝えるメッセンジャーとしての役割を果たしていたといいます。大変,有能で美人だったそうです。
さて,この美人で仕事もできるイリスを,まあ女性好きのゼウスがほっとくわけがないんです。ちょっかいをだしていきます。ちょっかいと言えばかわいいですが,もうストーカーに近い状態で,さすがのイリスも,これには,まいってしまいます。
ゼウスの求愛に困り果てたイリスは,ヘラに相談します。「ヘラ様お願いします。私をどこか遠くに行かせてください」
そうお願いすると,ヘラは「イリスよ,願いを叶えてもいいが,おまえの美しいその姿は消えて無くなるよ。それでもよいか。」というわけです。
イリスが「はい。それでもかまいません。」というものですから,ヘラはイリスの願いを聞き入れて,彼女に魔法のお酒をふりかけます。そうしたところイリスはたちまち虹になって,自由に遠くへどこでも行けるようになったんだそうです。その虹となって移動するイリスから,先ほどの神のお酒が地面にしたたり落ちて,その落ちた場所から水色のアガパンサスの花が咲きました・・・。アガパンサスはそんなお花です,というお話なのです。
この話,一説には,アガパンサスの花ではなく,アヤメの花だという説もあります。古代ギリシア語のイリスは英語で「アイリス」アヤメの花を意味しますからね。
さて,アガパンサスに話を戻しますと,ギリシア語で「愛」という意味を持つ「agape(アガペー)」がこの花の由来だと言う話をしましたが,古代ギリシア人ってゼウスみたいに恋多き人たちが多かったんでしょうか。「愛」意味する単語がたくさんあるんですよね。全部で8つくらいあるそうなんですがここでは3つほど挙げてます。
エロスという言葉も古代ギリシアでは「愛」を表す言葉ですけど,これはもっぱら男女間の愛情,恋愛を指すようです。また,フィリアという言葉はこれも「愛」と訳されますが,こちらは友愛,友情的な「愛」を意味する言葉のようです。
そして,このアガパンサスのアガペーですけど,これは,親が子を愛するような見返りを求めない「無償の愛」と言うのがもともとの意味のようです。
さて,いろいろある「愛」の概念の中でも,この「アガペー」の概念は,その後ヨーロッパの中心になる古代ローマ社会に受け次がれ,その古代ローマ時代に生まれたキリスト教に大きな影響を与えます。そして現代に至るまで欧米社会では,このアガペーは「究極の愛」とまでいわれその概念が非常に大切にされているのです。
見返りを求めないこの「無償の愛」がなぜ,欧米で,これだけ大切に考えられているのでしょうね?
それは,一つに,古代ギリシア思想の中に,「人間の世の中には,結構,不合理で不条理なことが多いものだ」ということがベースにあるように思えます。ギリシア神話などでは,先ほど話したゼウスに見初められてしまい,心ならずもその姿を変えてしまったイリスの話などもそうですが,しばしば,人間の理解を超えた現象や避けようもない運命の話などが描かれます。
例えば,古代ギリシアの詩人ホメロスが残した「オデュッセイア」という話では,戦争で勝利を収めたその最大の功労者だったのにもかかわらず,海の神の怒りをかった主人公が20年間もの間,故郷に帰れず,放浪の旅を続けることになったり,ソフォクレスが残した「オイディプス王」のお話では,息子の誕生を恐れた王様(神のお告げで「王様,息子さんが生まれるとあなたはその息子に殺されますよ」といわれたので息子の誕生を恐れたのですが)によって捨てられた息子が,成長して父親とは知らずにその王を殺し,その妃つまり自分の母親と結婚してしまうという悲劇的な運命をたどったりするわけです。
神々の気まぐれに翻弄される人間とか,その避けられない運命の残酷さとか,古代ギリシアの作品にはよく見られるんですが,その根底には,やはり現実の世の中にも不条理・不合理が存在していて,そういうものと人間は常に対峙しているんだという認識があるわけです。
だからこそ,古代ギリシアの人たちの間では,その不条理な運命に対して人間がどう向き合っていくのか,どう生きるのかということが大きな命題になっていくわけです。
さて,振り返ってみて,現代に生きる我々はどうでしょうか? 私たち自身の生活や社会の中にも,やはり,自分自身で一生懸命頑張っているのになかなか上手くいかないことがあります。自分自身の力ではどうにもならない不条理なことや不合理なことやも,大昔の古代ギリシアの時代ほどではないにしても,きっとあるでしょう。
その時に,私たちは,(君たちは)どう生きますか?ということなんです。
内に向かっていく悶々と,ずっと悩ましく生きていきますか?
「これは,自分のせいじゃない」と人に当たり散らして不平不満をぶちまけて生きていきますか?
やっぱり,「それではいけない」と昔のギリシア人も考えたんだと思うんですよね。古代ギリシアの人々は好んで「善く生きる」と言う言葉を使いました。
「善く生きる」とはどう生きるんでしょうね。スライドにあるようなソクラテスやプラトン,アリストテレスと言った古代ギリシアの哲学者たちがそれをまとめているのですが,それは,まず,知恵とか勇気とか正義とか優しさといった人間の魂に備わっている善い部分を磨くことが大切なんだと説いているんです。そして,それを十分に「発揮」せよと説いてます。もちろん,この際の「発揮」の仕方が大切で,ここでアガペーなんですね。ここが,無償の愛,見返りなどを求めない,見返りを考えないということなんです。見返りがなくても,自分が心を尽くして周囲の人々に対して分け隔てなく愛情を注ぐ,周囲に優しさを持って接することが大切だというわけです。
最後に,もう一度,アガパンサスの花を見てみましょう。確かに「愛の花」と呼ばれるだけあって,ニコニコとして四方八方にパーッと広がって愛情や優しさを振りまいている,見返りを求めずに降り注いでいるみたいですね。
さて,今座っている席の隣の人とニコニコと顔を見合わせてください。この花のように一人一人,自分自身が「善くありたい,善く生きたい,」と考え,優しい気持ちで,周りの友達と接してみてはどうでしょうか。また,家に帰ったら,家庭で,お父さん,お母さん,兄弟姉妹に同じような愛情や優しさを持って接してみてはどうでしょうか。
このことは,おそらく,周りの人たちの気持ちをよくすることでもあるんですが,自分自身の気持ちの安定につながるような気がします。愛情や優しさを周りに注ぐことによって,きっと自分自身の気持ちが軽くなって,自分自身が満ちたりていくような,そんないい効果を生み出すのではないかと思っています。
はい,それでは,これにて,7月の校長講話を終わります。
今年は梅雨明けも早くて,暑い日が続きますけど(この暑いことも一つの不合理・不条理かもしれませんけど),そんな中にあっても,いつもニコニコと元気よく,人に優しく愛情をもって過ごしてほしいと思います。
現実の世の中に自分の力ではいかんともしがたいことがあるとしても,自分の内面だけは,自分自身でよくしていくことができますからね。
皆さん,7月も頑張りましょう。これで終わります。
全校朝会3(令和7年6月9日)
今日の全校朝会は,私のお話だけの予定だったんですけど,部活動生の皆さんが本当によく頑張ってくれて,もともと予定してあった6月後半の表彰式・壮行会だけでは,皆さんの表彰伝達・披露が終わりそうにないため,今日は,その一部を実施させてもらうことにしました。
今日も多くの部活動の皆さんに表彰状等を渡すことができて本当にうれしく思います。この時期,多くの部活動が3年生の最後の大会となっているわけですが,引率に行った先生方にお聞きすると,どの競技においても最後となる3年生が本当によくチームをよくまとめてくれて引っ張ってくれて,いい形で次の1年生,2年生に,引き継ぐことができたと聞いています。
今日は,まず,競技や活動を終えた3年生の部活動生に向けてお話をしたいと思います。
皆さん,本当にお疲れ様でした。そして,ありがとう。
皆さんには,部活動の先輩として後輩たちに,鶴丸高校の部活動のあるべき姿,部活動生,鶴丸生のあるべき姿を示し,伝えてもらったのではないかと思います。君たちの姿を見て,きっと後輩たちも意気に感じて,それぞれの部活動の伝統を引き継いでくれることでしょう。
「先輩」というのも少し辛いところがあるものですよね。「先輩だからしっかりしなきゃ」とか「先輩だから下手なことはできないとか」とか…。
でも,これまで,よく頑張りましたね。もう,この後は,周りの人に気をつかったり,周りに合わせたりする必要はありません。この後の時間は,自分自身のために,自分自身の夢を実現するために頑張ってください。
このようにお話しながらも,3年生の中には,まだ引退していない部活動生もいますよね?
野球部は7月5日から最後の夏の大会,吹奏楽部や音楽部は7月末から8月初めにかけてがコンクールだと聞いています。この時期に,周りの友達は次々と「部活を引退しました」となってきて,焦る気持ちもあるかもしれないけど,心配しないで落ち着いて頑張ってください。きっと大丈夫です。
そもそも「あーどうしよう」って悩み,考えてる時間がもったいない。2つ以上の仕事を瞬時に切り替えながら,もしくは同時並行で仕事を行うこと,いわゆるマルチタスクをこなしていくことは,君たちが大人になって仕事をするようになれば,そういった場面がとても増えてきますし,それが強く求められてもきます。
そういう状況にあるときには,やはり,目の前のこと一つ一つに集中することが大切だと思います。ボール追いかけているときは全力でボールを追いかければいい,楽器を演奏するときはいかにいい音をだそうか,そのことに集中すればいい。家に帰って勉強するときは,本当に無駄な時間を省いて一問一問に全精力を傾け集中して臨む。そのような意識を持って頑張っている人の方が,だらだらと時間をかけるより質のいい勉強ができているかもしれませんよ。
部活継続中の3年生は,今の時期の,この状況は,自分が時間を管理する良いトレーニングの機会が与えられたと考えればどうでしょうか。時間を自分が操るのです。しっかりと時間をマネジメントできた人は,部活が終わったときに,ああこんなにも時間があるんだということに気づき,いい時間の使い方ができると思います。これから,最後の部活の大会に向け,何事にも集中して頑張ってください。
では,1年生・2年生にもお話しをします。私は昨年も2年生には言いましたが,部活動は,主体性を育んだり,困難な状況にあっても粘り強くやり抜く姿勢であったり,また他者と協働しながら課題を解決する姿勢を学ぶという観点から大切な活動だと考え,入部している皆さんにはその活動に意味があるように取り組んでほしいと思っています。
ただ,誤解のないように言っておきますけど,部活動については,大事な活動だから,全員,部活動に入ってほしいとか,部活動に入りなさいということではないですからね。通学の関係で入りたくても入れないという人もいるでしょうし,部活動よりも,学校外の習い事でずっと頑張っているという人もいるでしょう。また,学業・勉強以外の時間は自分の時間に,例えば,たくさん本を読みたいんです,とか,自分の幅を広げるような,部活動よりも,そんな時間に使いたいという人は,それはそれでいいと思います。また,予習をしっかりする,学校で習ったことを復習して習得する。ひたすら,今頑張っている学業を深めたい,勉強にかける時間がもっともっとほしいので部活は入っていませんという人は,それはそれで堂々と,大いに頑張ってほしいのです。
部活動の加入は任意ですからね。入部していないからといって引け目を感じることはありません。部活動との向き合い方はそれぞれがしっかり考えてください。
部活動に入っていない生徒の皆さんには,体育祭とか文化祭とかの学校行事で主体性を身につけたり,また他者と協働しながら課題を解決する姿勢を学ぶということはできますからね。そういう意味で部活動も学校行事も授業も全部含めて「学校」というところ「学校にいる」ということを大事に考えてほしいと思います。
今日のお話はここまでとします。
6月は梅雨の時期ですが,健康に留意して皆さん元気に頑張っていきましょう。2年生は今月18日からの修学旅行を是非楽しんできてください。
以上です。
全校朝会2(令和7年5月12日)
令和7年度がスタートして1か月が経ちましたが皆さん,いいスタートが切れているでしょうか。特に,1年生はどうですか。みんなが,「学校が楽しい」「鶴丸高校に入学して良かった」と言ってもらえれば嬉しいですが,実際は,高校の学習内容について行けるかどうか不安だったり,周りの友人が,みんな能力が高く見えて,自分はダメなんじゃないかと自信を失ったりしている人もいるのではないでしょうか。
2年生3年生も含めてなのですが,今日は,特に,そんな少し弱気になっている人に向けてお話をしてみたいと思います。
日本の若者は「自己肯定感が低い」とか「自尊感情とか,自己有用感とかが低い」という話を聞いたことがあるでしょうか。本当なんですかね。低いと悪いんですかね。高けりゃいいんですかね…。
まずは,本当に「日本の若者が自己肯定感とか自己有用感が低いのかということを各種のデータをみて確認してみましょう。
まず,全校朝会2資料[PDF]の1ページ目です。これは少し前の平成25年度の内閣府の調査です。ここの「若者」は各国13歳から29歳までの若者を対象とするようです。「私は,自分自身に満足している」という項目に対して,明らかに,他国と比べ,日本の満足度の低さが目立ちますね。
2ページ目は国立青少年教育振興機構というところの平成26年度の調査です。「自分はダメな人間だと思うことがある」については,この結果です。
この数値は,他国に比べ高い数値がでていますね。
次は,先進国38カ国が加盟する経済協力開発機構(OECD)のホームページの画面です。ここはよく加盟国間の15歳の子供の学習環境等の調査を行うためPISA(ピザ)と呼ばれる学習到着度調査を実施することで知られます。このホームページは2022年に公開されたもので,子供のウェルビーイング(良い状態)を判断する指標を設定し,それぞれの指標の状況について学習到着度調査の結果などをもとにOECD加盟国間の比較をしたものです。3ページ目はそのHPの画面,4ページ目の資料は,これをもとに文科省等が作成した資料になります。この4ページに日本の状況が概要で示されています。
やはり,この調査でも自己肯定感・自己有用感に係る数値は,国際間の平均と比較して日本はかなり低い状況にあります。ただ,注目してもらいたいのは,日本の子供は「成長意欲がある子供の割合」が高いという結果がでているということです。
これ,自分はダメだと思いながらも「もっとできるようになりたい」,「もっともっといろいろなものを吸収したい,勉強したい」と思っているわけですから,そこは期待できると思うのです。期待できるというか,理想とするところが崇高で目標がレベルが高い所にある人が,そこに到達できないことを「ダメだった」「満足できない」と思うことは極めて健全なことだと思うのです。大切なことは,「『理想としている自分』『期待している自分』と今の自分とのギャップをどうすれば埋められるか?」その手立てを考えることだと思うのです。
さて,もう少しデータを見てみましょう。6ページ目は鹿児島県のホームページに掲載されている全国学力学習状況調査の中学生の結果から作成した資料です。これは令和6年度の中学3年生が調査対象のものですからここにいる1年生の皆さんが受けたものになります。この調査,全国の学力と比較して鹿児島の小中学生の学力はどうかということばかりが注目される資料ですが,私は,この調査で生徒や先生方(学校に)にとるアンケート結果に注目をしているんです。
この資料は,全国平均と比較して鹿児島の中学生はどうかということなんですけど,「自分にはよいところがあると思いますか」という自己肯定感的なものを問うこの質問,世界的に見ても自己肯定感的が低いと思われる日本の中でも,鹿児島はその日本の平均と比べても4ポイント程低いという結果が出ています。
でも,さっき言ったとおり,私は「自己肯定感が低い」というこれをもって全て悪いとは思っていないんです。鹿児島の子どもたち,鶴丸高校の生徒たちには「理想としている自分,期待している自分と今の自分とのギャップをにどうすれば埋められますか?」「どうすれば理想としている自分になれますか?どうすれば自分の期待に応えることができますか?」ということを考えてほしいのです。
このデータに結構いいヒントがあってですね,鹿児島県が全国と比べて3ポイント以上水をあけられた項目がこの通りなんですよ。「自分の考えを発表する」「話し合い,お互いの意見の良さを生かして解決方法を探る」「スピーチやプレゼンテーション」この項目が差をつけられたんですよね。
本県の生徒が苦手としている学習活動は,ほぼ「発表」だとか「スピーチ」だとか「プレゼン」だとか「話し合い」なんですよ。すごくはっきりしていますよね。
さて,この力,当然「他者との関わり」なしでは身につかないものなのです。私,学校の存在意義は今やこの1点に尽きると思っていて,でも絶対に外せない1点だと思っているんです。知識を伝授してもらうだけなら今や配信授業だけでも何とかなるかもしれない時代なんですよね。でも,大切なことは,人間は,生身の人間とのやりとりの中で生きていて,その人と人との関わりの中で何かをつかんだり,何かを解決していくようなそのような,そんな力こそが,これからの私たちには求められているのだと思います。また,これが,これからの学校教育の大切な仕事になってくると思っています。
だから,授業では,私も去年から先生方にお願いしていることなんですが,授業の中においても,先生方側が,一方的な講義形式だけを行うのではなく,皆さんに発表させたり,話し合いを持ったりと他者との関わりの中で課題解決していくようなそのような,そんなアクティブな学習活動や場面を多くしてもらえるようにお願いをしたところです。また,さっきの質問項目(6ページ目)の最後の項目の「鹿児島の先生方は生徒のよいところを認めてくれていると思いますか」という項目が全国に比べてかなり低かったので,先生方には生徒を褒めてあげてくださいとお願いしておきたいと思います。
1年生は,少しは,周りの友達とお話ができるようになりましたか。特に,違う中学校から来た友達とか,全く面識がなかった人と勇気を出して話しかけてみてくださいね。内向きにならず,他者との関わっていく姿勢や態度がこれからの時代に必要です。でも,他者と関わることは,不用意な言葉で相手を傷つけないかとか,案外難しさもあるんですね。そのときは,前回の全校朝会でお話しした,「自律敬愛」,特に「敬愛」の精神で,お互いがお互いを思いやり,お互いが一人の人として尊重しあってほしいというお話を思い出してみてください。
最後に,最後の8ページ目のシートを見てください。ちょっとネガティブなデータが多かったですが,この資料については,鹿児島の生徒たちが全国平均を大きく上回った項目をまとめたものです。一番大切な,健康の部分,生活リズムの確立の項目で他県を大きく上回る結果が出ていること,学校での学習が自分のためになっているという前向きな気持ちを持って学校生活を送っていること,そして,何よりも鹿児島の子どもたちは,「将来に対して夢や目標を持っている」という項目が全国を大きく上回っていることは,私自身,鹿児島の子供たちを誇らしく思うことでした。皆さんも自信を持って頑張ってください。
以上,今日のお話は終わりです。
今月5月下旬からは,早くも3年生の多くの引退試合となる高校総体が各競技ごとに始まっていきます。3年生の各部活動生も1日1日悔いのないように過ごしてください。
令和7年度 PTA総会 校長挨拶(令和7年5月9日)
皆様,こんにちは。校長の黒木でございます。
本日は大切なPTA総会の冒頭の時間,この後,新役員の選出など大切な協議等も予定されているところですが,私も今年度,皆様方にお会いするはじめての貴重な機会でございます。
PTA会長様にお願いし,少し,お時間を頂きましてご挨拶を兼ね,学校の経営方針や校長としての私の思いなどを少しお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。
さて,今年の3月,国の新年度予算を巡る政党間の折衝の中で,少々思わぬ形でしたけれど,突然,注目を集めた内容に,高等学校に対する就学支援制度拡充の問題がございました。これまで世帯収入910万円未満の世帯の生徒さんの家庭はこの就学支援制度の対象になっていて授業料相当分の金額が支援されておりましたが,この春からは,所得制限が事実上撤廃され全世帯がその対象となりました。いわゆる公立高校の授業料は実質完全無償化です。
また,予算案を検討したときの政党間の合意により来年度以降は私立高校の支援が手厚くなっていくことになりそうですので,これから高等学校への進学を控えてらっしゃるご家庭では,公立・私立の別なくその選択肢が広がっていくことになるのだろうと考えているところです。
今後は,公立・私立関係なく,高等学校の各学校1校1校が,それぞれの学校の更なる魅力向上に努め,「私たちの学校はどのような学校で,どのような生徒を育てたいのか,私たちの学校は何を目指しているのか」ということを明確にしてお伝えすることが益々大切になっていくのだろうと感じています。
そういう意味でも,今年は,少し丁寧に本校の学校経営方針等について,説明させていただきます。
では,PTA総会資料[PDF]の1ページ目「令和7年度学校経営方針等について」をご覧ください。
まず,レジメの1に書いてあります「建学の理念・校是」です。 (1)「好学愛知」(2)「自律敬愛」(3)「質実剛健」の3つは「校訓」という表現は使わず本校では「建学の理念」と読んでいます。
校是はご存じ「フォー・アザーズ」,他者のため,社会のため,世の中のために,という精神です。
2の「教育目標」は,憲法や教育基本法,本校の建学の理念を踏まえて定めたものになります。
「不易と流行」という言葉がありますが,1の建学の理念や2の教育目標とかは「不易」の部分だと思うのです。これは,校長が替わったからといってそうそう変えるもの,変わるものではありません。
一方,現代は,そしてこれからの時代は,少子化,情報化,国際化が進み,予測することが難しい時代だとも言われています。
本校の創立は,旧制中学校からの発足からすると130年前の明治時代。この建学の理念とか教育目標だけだと,時代に合わない部分とか,アップデートできない部分,言葉が足りない部分などが,やはり出てきます。時代の変化や今日的な課題に対応するために,新たに教育目標に掲げていくものや,これまで目標に掲げてきた項目の中でも,今の時代だから,特に,これを強調しておく,付け足しておくということも当然必要になってきます。「不易と流行」の「流行」の方をどうするかということですね。
このような状況を受け,実は,学校教育法の施行規則等が変更されまして,まず,県の教育委員会で,所管するそれぞれの高校について,当該校に期待される社会的な役割 =「スクール・ミッション」を策定しなさいということになりました。これが3になります。
そして,それに応じて,各学校は,①卒業までに育成を目指す資質・能力に関する方針,②教育課程の編成等に関する方針,③入学者受入れに関する方針の3つの方針 =「スクール・ポリシー」を令和6年度までに策定し,しっかりと公表しなさい,ということになったのです。
ですから,3のスクール・ミッションと4のスクール・ポリシーは昨年度から新たに,この場で紹介させていただいているということになるわけです。
さて,今日,一番お話をしたかったのが,「4 スクール・ポリシー」の中でも下線部を付した(1)の3つです。これは,本校の3つの建学の理念を今日的に解釈・整理し,それぞれに文言を肉付けして「本校の目指す卒業までに生徒に身につけてもらいたい力=資質・能力」を示したものになります。
3つともにそれぞれに大切なのですが,今,個人的に特に力を入れなければと思っていることがありまして,先日も全校朝会で生徒たちにその話をしたところです。それは,この3つのうちの真ん中の4の(1)のイの箇所,建学の理念の第2【自律敬愛】を今日的に解釈した「自らを律し,能動的に考えて行動する力を身につけると共に,他者の個性を尊重し,多様な人々と協働して学ぶ力を育成します。」の項目です。これを,年度当初にあたって,生徒たちには少し意識し考えてほしいとお願いをしました。
最近の社会の様子を見たときにSNS等の発達もあるのでしょうか。誹謗中傷・ハラスメント・不適切な言動で人を傷つけ,傷ついて・・・ 相手の思いや立場,関係なしに独りよがりの考え方で自分の考える正義だけを振りかざす・・・そんな場面が多いように感じるのです。
昨年度の社会的な事件で「闇バイトに参加してお年寄りなどを傷つける若者のニュース」などもありました。昨日は昨日で,「保護者の知人が小学校の教室に侵入して暴力行為に及ぶ」という事件もあったところです。どうして,そう簡単に,言葉もですけど,暴力まで使って人の尊厳を踏みにじる,傷つけることができるんでしょうか。
先日生徒たちには,「自らを律し,思いやりを持つ,お互いがお互いを思いやる気風,この【自律敬愛】の項目こそ,今の時代に大変重要な項目で,一人一人の性格とか,その人が生活してきた環境とか背景とかみんな,それぞれにそれぞれの立場や状況があるけれど,そこを越えて一人一人がお互いに認め合い,協力していくことができるそのような態度や姿勢を身につけてもらいたい」ということを呼びかけたところです。
この問題を考えるときに,やはり,学校の場において,私たちがやらなければならないことは,それぞれの人格や人権が大切にされる環境をしっかりと整えることだと思っています。
「鶴丸は勉強するところである」なんですけど,その前提として,学校という場所が,常に,誹謗中傷とか「いじめ」等の問題もなく「安全・安心な状態にあること」「生徒の皆さんの心の中が安定した状態にあること」が学力の定着・向上につながることはもちろん,健康の増進・体力の向上,部活動の上達だったりにも,必ず繋がっていくものだと思っています。
生徒の皆さんが,安心して伸び伸びと教育活動を行い,自らの持てる力を十分に発揮し,更なる資質と能力を,ここ鶴丸高校で開花させることができる。そのような環境作りを学校としてもしっかりと心がけてまいりたいと思います。
さて,最後に,今年,入学式に参加された1年生の保護者の皆様,入学式はどのような感想を持たれましたでしょうか? 私の知り合いの保護者の方とお話をしたら,「あの校歌紹介がよかったです」と言っていただいた方がいました。あの「校歌紹介」,今の2年生,3年生の保護者の方々も同じようにご覧になられたと思いますが,音楽部の生徒を中心に校歌「はろばろと」が成立した由来を説明した上で歌っていくスタイルですが,ナレーションや練習すべて生徒中心に行われています。私から見ても本当に感動的な校歌紹介で,自分の学校の生徒たちをこのような場で褒めるのは恐縮ですが,本校の生徒たちを誇らしく思うことでした。
私たちの学校の魅力や強みは,旧制一中と旧一高女の時代,そしてその後,両校が統合され,戦後は男女共学の学校として卒業生の方々が作り上げてこられた歴史と伝統,そしてその雰囲気が醸し出す「校風」が脈々と受け継がれていること,また,「フォーアザーズ」の精神に基づき,「学業を極める」と言うことだけでなく人間形成・人格の完成を目指した教育が行われているという点にあります。
冒頭,「私たちはどのような学校で,どのような生徒を育てたいのか,私たちの学校の魅力とは…」という話をしましたが,今年の入学式を見ながら,この鶴丸高校の魅力やその強みは,既に強固なものがあるわけですからこれをしっかりと周知・広報していくことがまず大切なのだろうと考えています。この点については,これまでのホームページやブログだけでなく,昨年度からSNS等でも学校の取組を紹介させていただいているところです。
また,学校の魅力の周知に欠かせないのが皆様方,保護者のお力です。皆様には本校の広報担当として中学生や小学生をお持ちの保護者の方々などに本校の取組や魅力等を積極的にお伝えいただければありがたいです。
鶴丸高校の魅力が,この後100年も200年先も受け継がれるよう今年度も,職員一同,生徒たちのために力を尽くしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
すみません。少し長くなりましたが,以上で私からのお話とさせていただきます。
本日の協議は,昨年度の諸活動及び今年度の予算案等と新役員の選出があるようです。また,学校からは学校評価や生徒指導・進路指導についての説明等をさせていただきます
閉会後は,長らく役員としてご尽力していただいた方々への表彰も行われるということであります。
本日のPTA総会が実り多きものとなりますよう,また,今年度の本校の教育活動に対しましても,これまで同様,ご理解ご協力を賜りますことをお願い申し上げまして,私のお話とさせていただきます。
本日は,どうぞよろしくお願いします。
全校朝会1(令和7年4月21日)
新学期が始まり,2週間がたちましたが,新しい環境には,少し慣れてきたでしょうか? 始業式,入学式に始まり,中身の濃い2週間だったと思います。いろいろとお話したいことがありますが,今日のこのタイミングですから,まずは,先週金曜日に行われた甲鶴戦についてふれておきます。
甲鶴戦は本当に素晴らしいものになりました。半年前から準備をしてくれた生徒会の皆さんにまずはお礼を言いたい。本当にありがとう。また,応援団の皆さんもよく頑張りました。皆さん,格好良かったですよ。選手として出場した体育会系の部活動の皆さんのお疲れ様でした。設営・準備に尽力した文化系の部活動の生徒にも感謝しています。
甲鶴戦の閉会式では,本校の生徒会長がいい話をしてくれました。
・ ただ勝った,負けたではなく,お互いをリスペクトして,同じ仲間である
という気持ちを持ちましょう。
・ 嬉しかった,楽しかった,逆に上手くいかずに悔しかった,悲しかったということも,
これからの生活を過ごすための糧にしていきましょう。
本当に,その通りだと思います。鶴丸高校生は鶴丸としての帰属意識,また鶴丸・甲南の生徒は同じ鹿児島の切磋琢磨する仲間であるという意識を醸成することが甲鶴戦実施の目的でもあります。
甲鶴戦を,ただ実施した,ただ,どちらが勝った負けたということだけでなく,この学校行事で経験したことをそれぞれがどのように咀嚼し,消化していくか。これが大切なことだと思います。
とはいえ,私自身は,そんなにできた人間ではないものですから,総合成績で負けてしまったこと。続いている連敗を止められなかったのは,まあ,やっぱり残念で複雑な思いもあります。
1年生,2年生,来年は頑張ってほしい。甲鶴戦の勝利は,ここ数年かけても解けない宿題のようなものかもしれません。1年生,2年生にこの宿題を託したいと思います。
3年生の部活動生は,いよいよこの夏で部活動も引退です。夏に行われる最後の大会に向けてこの甲鶴戦での反省点などをこれからの練習に生かしてください。
さて今日は,年度初め,3学年全員が揃った初めての全校朝会です。今日は,本校の学校経営方針について~「鶴丸高校はどのような生徒を育成しようとしているのか?」「どのような教育を行おうと,どのような教育を目指そうとしているのか?」~ という話をします。
学校経営方針についてなんて話は,大人向けの話では?校長先生が先生方とか教育委員会に説明したりするものでは? と思うかもしれませんが,このことを一番に理解してもらいたいのは君たちなんです。
まず,2枚目のシートから見てください。これは4月初めに職員会議で先生方に対して示した資料「学校経営方針」です。
最初に「1 建学の理念・校是」ですが,本校の好学愛知・自律敬愛・質実剛健は「校訓」とは言わないんですね。「建学の理念」といいます。
そして「校是」,これは学校のモットーと言いましょうか。校是は「For Others(フォー・アザーズ)」です。
また,「2 教育目標」は,憲法や教育基本法,そして本校の建学の理念を踏まえ,設定しています。
「不易と流行」という言葉があります。教育の世界でも「教育の不易と流行」という言葉をよく使うんです。
1枚目のシートに戻ってください。ここにあるように「不易」というのは,時代を超えて変わらない価値のあるもの,例えば,「真理を求める態度」であるとか「豊かな人間性」,「健やかな身体」といったものです。これは今も昔も学校教育が目標としなければならない大切な価値のあるものです。
一方,現代は,そしてこれからの時代は,少子化,情報化,国際化が進み,予測することが難しい時代だとも言われています。「流行」の方は,このような時代の変化と共に,今,この時代に求められている資質・能力を整理して提示していくものになります。
本校の建学の理念や教育目標とかは「不易」の部分だと思うんですよね。やはり,これは,校長が替わったからといってそうそう変えるもの,変わるものではありません。
でも,本校の創立は,旧制中学校からの発足からすると130年前の明治時代。鶴丸高校となってからも約80年経っています。この校訓とか教育目標だけだと,時代に合わない部分というかアップデートできない部分がやはり出てくるんですね。また,いろいろと身につけるべき資質・能力の項目の中でも,今の時代だから,特に,これを強調しておくということもあります。
このような状況を受け,実は,近年,国の法律等も変わり,まず,県の教育委員会で,所管するそれぞれの高校について,当該校に期待される社会的な役割 =「スクール・ミッション」を策定しなさい。そして,それに応じて,各学校で,1.育成を目指す資質・能力に関する方針,2.教育課程の編成及び実施に関する方針,3.入学者の受入れに関する方針の3つの方針 =「スクール・ポリシー」を策定し,「公表しなさい」ということになったのです。(だから,今こうやって君たちに「公表」しているわけです。)
それぞれの学校の「校訓」や本校でいうところの「建学の理念」が,それぞれの歴史とか伝統とかを踏まえて脈々と受け継がれていくものだとするならば「スクール・ポリシー」は今日的な課題(学校を取り巻く環境の変化だとか,時代の流れとか)を踏まえて,逐次見直しながら設定していくものになります。
さて,私たちの学校で策定する「スクール・ポリシー」の中でも,今日,特にお話ししたいと考えているのは,「4 スクールポリシー」の(1)の「グラデュエーション・ポリシー = 卒業までに皆さんに身につけてもらいたい力=資質・能力」なんです。
そして,今年,個人的に力を入れたいと思っていることが,4の(1)のイの箇所,もう少し具体的に言うと,特にイの文章の後段の部分,「他者の個性を尊重し,多様な人々と協働して学ぶ態度を育成します。」これをしっかりとやっていきたいのです。君たちにそのような態度を身につけてもらいたいんです。先ほど,甲鶴戦の閉会式で生徒会長が,「お互いにリスペクトして」という話をしたんですけど,まさしく,これなんですよね。
「スクール・ポリシー」って,学校を取り巻く環境の変化だとか,時代の流れとか,今日的な教育課題を踏まえて逐次見直しながら設定していくものだと言いましたよね。
最近の社会の様子を見たときにSNS等の発達もあるのでしょうか。誹謗中傷・ハラスメント・不適切な言動で人を傷つけ,傷ついて・・・と言う場面を多くみることがあります。昨年度の社会的な事件で「闇バイトに参加してお年寄りなどを傷つける若者のニュース」などもありました。どうして,そう簡単に言葉もですけど,有形力まで行使して人を傷つけることができるんでしょうね。そして,私たちが携わっている学校教育の喫緊の教育課題は,やはり,「いじめ」等の問題だといわれています。私たちは,これを何とかしたいのです。
この問題を考えるときに,やはり,学校の場において,それぞれの人格や人権が大事にされる環境をしっかりと整えること。そして, ~ その人の性格とか,その人が生きてきた人生とか,いろいろな背景とか,みんな,それぞれにありますけど,~ そこを越えて様々な立場の人々がお互い協力していくことができるそのような態度を身につけてもらえる環境を整えることが大切だろうと思っています。
自分の尊厳であるとか,自分の背景にある大切にしているものとかがないがしろにされるのって嫌ですよね。理不尽にひどい言葉を浴びせられたり,傷つけられたり,耐えがたいですよね。
自らを律し,思いやりを持つ,お互いがお互いを思いやる気風=本校の建学の理念の2番目「自律敬愛」を今日的に解釈したこの項目について,私は今年これを大切にしたいと思うのです。
「思いやり」といいましたけど,これを考えるとき「言葉」って非常に大切なんですよね。不用意な言葉で本当に人を傷つけてしまうことがないようにということも大切でし,逆にある人の「思いやりのある言葉」で救われることもあります。その人の言葉で,周りの人が元気になるような,明るくなるような,一緒に頑張ろう,っと思ってもらえるような,そんな言葉を持っている人,使えるような人になりたいですね。
私もそうなれるようにと思っているんですけど難しいですよね。やっぱり本を,特に美しい文章の本を読むことが役に立つかなと思います。また,高校生に戻れるなら国語の授業でそんなセンスを磨きたいなあ,勉強し直したいなあと思ったりします。
皆さん,もし,今,人間関係につまずいたりして,学校にいることに息苦しさだとか何かおかしいなと思ったら,担任の先生や話をしやすい先生方に声をかけてくれないでしょうか? 私たちは,必ず君たちの力になりたいと思います。
「鶴丸は勉強するところである」なんですけど,その前提として,学校という場所が,常に,いじめや誹謗中傷等の問題もなく「安全・安心な状態にあること」そして「皆さんの心の中が安定した状態にあること」が,学力の向上はもちろん,健康の増進・体力の向上,部活動の上達だったりにも,必ず,つながるものだと思っています。
皆さんが,安心して伸び伸びと教育活動が行える,皆さんが持っている自分たちの持てる力を十分に発揮し,更なる資質と能力を,ここ鶴丸高校で開花させることができる。それが,鶴丸高校の役割だと思っています。今年はこの点に力を入れていきたいと思います。
さて,今日は3時間目4時間目は創立記念式があります。記念講演会は,現在,宮崎大学の学長をされている本校の26回卒業生の鮫島先生です。初めて3学年揃って体育館で校歌を歌います。鮫島先輩の前で大きな声で,心を込めて歌ってください。よろしくお願いします。
これで今日の全校朝会の講話を終わります。
第55回甲南・鶴丸スポーツ交歓会開会式挨拶(令和7年4月18日)
甲南高校の皆さん,おはようございます。
鶴丸高校の皆さん,おはようございます。
スポーツの交歓を通して両校の親睦をはかり,それぞれ甲南高校生・鶴丸高校生として自覚と連帯・帰属意識を深めるということを目的にして開催されている本大会も今年で55回目を迎えることになりました。
「紅華紫麗 紅の燃焼,紫の深遠」のキャッチフレーズの元,甲南・鶴丸スポーツ交歓会を,今年度も無事開催できますことを本当に嬉しく思います。
今日の甲鶴戦を開催するにあたり,私から3つお願いをしておきます。
一つは,出場する選手の皆さんへのお願いです。今日このような場を設けていただいていることに感謝の気持ちを持って競技に臨んでくださいということです。感謝の気持ちを持って,心のこもった全力でのプレーをお願いします。皆さんの姿が,多く人に感動をあたえてくれることを期待しています。
二つめは,応援の生徒の皆さんにお願いします。今日の甲鶴戦の場は,いろいろな種類のスポーツ競技について,それぞれのルールや見所,そしてその競技の面白さを学べるという機会でもあります。今やスポーツは「する」だけでなく「見る」「支える」という観点から誰もが参加できる一つの文化となってきています。ただ応援すると言うだけでなく,保健体育の学習の一貫として,また,自らの知識や教養を深め人生を豊かにするという意味においても,今日は「学ぶ」という視点を持って観戦してもらいたいと思います。
そして,三つめ,これが一番大事なお願いです。
今日の「この1日を」「この甲鶴戦を」思う存分,楽しんでください。
楽しむためには,まず怪我のないこと,熱中症に陥るなどの事故がないことが大切です。選手の皆さん,プレー中に危険を察知したら必ず声をあげて知らせてください。応援の生徒の皆さんも各会場,距離がありますので,会場間の移動の際には,交通事故等にも気をつけてください。
以上,今日の甲鶴戦が両校にとって充実したものとなることを願っています。
最後になりますが,今日のこの甲鶴戦の運営に携わられた両校の担当の先生方,生徒会の皆さん,応援団の皆さんに感謝するとともに,会場関係者の皆様や各競技団体の審判員の皆様にも御礼申し上げます。
そして,ご来場の保護者や卒業生の皆様方には,本日,甲南高校・鶴丸高校,両校の選手に熱い声援を賜りますよう お願い申し上げて,第55回甲鶴戦のご挨拶とさせていただきます。
皆さん,今日はよろしくお願いします。
令和7年4月18日
鹿児島県立 鶴丸高等学校
校長 黒木 誠
令和7年度 入学式 式辞(令和7年4月8日)
暖かな春風の中,校舎を取り巻く木々にも新緑が芽吹き始める陽春のこの佳き日にご来賓,保護者の皆様のご臨席を賜り,令和7年度鹿児島県立鶴丸高等学校入学式を挙行できますことを職員一同心から感謝申し上げます。
ただ今,入学を許可しました320名の新入生の皆さん,入学おめでとうございます。本校の一員となられたことを祝福いたしますとともに,教職員並びに在校生一同,皆さんを心から歓迎いたします。
さて,新入生の皆さん,本校の建学の理念をご存じでしょうか。この体育館の皆さんから見て前方左上に掲げてあるとおり「好学愛知」「自律敬愛」「質実剛健」の三つの理念です。今日の入学式では,このうち第一の「好学愛知」について,そして,これに関して,本校に伝えられている「鶴丸は勉強するところである」という言葉についてのお話をします。
今年は,太平洋戦争が終結した昭和20年(1945年)からちょうど80年,戦後80周年を迎える節目の年にあたります。終戦後,社会の様々な制度が変わっていく中で,学校制度の在り方も大きく変化することになります。戦前の5年生課程の旧制中学校は,新しい学制のもと,3年課程の高等学校へと変わりました。本校は,昭和24年に旧制鹿児島県立第一鹿児島中学校と旧制鹿児島県立第一高等女学校が統合する形で「鶴丸高校」として発足した学校になります。
その翌年の昭和25年,本校は初めて新制中学校からの新入生を迎えることになるわけですが,その入学式後の新入生と上級生との対面式において,当時の生徒会長が,新入生に対して語った言葉がこの「鶴丸は勉強するところである」だと言われています。
当時の鶴丸高校3年生の生徒会長は徳満さんというお名前の方らしいのですが,この徳満さんは,後に,この言葉だけが一人歩きしてしまって,少し誤解をされて受け止められているという旨のお話もされています。
この言葉に込められた思いを考える上で,当時の時代背景を知っておく必要がありそうです。
昭和25年当時の高校3年生は,その5年前の昭和20年,終戦の年には旧制一中の1年生としてこの薬師の地で学生時代を過ごした学年になります。昭和20年は,その年の3月以降,鹿児島市内においても激しい空襲が繰り返され,6月17日の空襲では,この場所にあった本校の校舎も焼失しています。また,この時期の旧制一中の生徒たちは県内外の工場に動員されて労働に従事したという記録も残っていますので,学生が学校に来て勉強する,学校生活を送るという当たり前のことがなかなかできない状況だったのです。
戦争が終わり,新しい鶴丸高校が誕生したときに,当時の生徒たちは自分たちが高校で学んでいる,学ばせてもらっているということに対して感謝の気持ちを感じていたのだと思いますし,一生懸命に学ぶことによって,戦争で疲弊した日本の国を,私たち若者の力で新しい,よりよい国にしていきたいという大きな志があったのだろうと思います。
鶴丸高校に入ってきた新入生に対して,当時の上級生たちは,「新入生の皆さん,ここ鶴丸高校は,皆さんが安心して勉強ができるところですよ」,「新入生の皆さん,自分のやりたい勉強を思う存分やってください」,「新入生の皆さん,勉強をやるからには周囲の方々に感謝の気持ちをもって真剣に取り組んでください」
そんな思いが,当時の生徒会長の言葉に込められていたのだと思います。
勉強ができることこそは,自由で平和な時代の証なのです。
皆さん,高校入試に向けての受験勉強は辛かったですか。苦しかったですか。勉強が辛く,苦しい,そのような面は確かにあると思いますが,「学ぶ」ということは,そのことによって「知らなかったことを知ることができる」「できなかったことができるようになる」「自分自身の視野が,世界が,広がっていく」という,本来は,人として,「楽しく」「素晴らしく」「尊い」ことなのだと思うのです。
新入生の皆さん,私たちの学校には,建学の理念に加えて,校是としている「フォー・アザーズ(For Others)」と言う言葉があります。「他者のために,世の中のために」という精神です。
皆さんには,入学後も,いろいろなことをお話ししたいと思っていますが,今日の入学式では,皆さん一人一人がよりよい社会を創るため,我が国や世界をよりよいものにするためにという高い意識と高い志をもって,知を愛し,学ぶことを好む鶴丸高校生になってほしいということをお願いしておきたいと思います。
これから始まる授業や学校行事,部活動や生徒会活動などの様々な場面においてここ鶴丸高校に集った仲間達とともに,学び合い,高め合って,共に成長していくことを心から願っています。
保護者の皆様,本日はお子様の本校へのご入学,誠におめでとうございます。心からお祝い申し上げます。併せて創立から百三十年余りの伝統を持つ本校での学びに信頼と期待をもってお子様をお預けいただきますことに深く感謝申し上げます。
保護者の皆様が安心してお子様を本校に通わせることができるよう,我々教職員一同,生徒たちが安全に,安心して学べる環境を整えるとともに,お子様の持つ優れた資質・能力を更に引き伸ばすことができるよう力を尽くして参りたいと思います。
保護者の皆様方におかれましても,本校の教育方針を十分にご理解いただきますとともに,学校が意欲的に教育活動に邁進できますよう,ご支援とご協力をお願い申し上げます。
結びに,本校の教育活動に対し,温かいご理解とご支援を頂いている関係各位に感謝とお礼を申し上げ,式辞といたします。
令和七年四月八日
鹿児島県立 鶴丸高等学校
校長 黒木 誠
令和7年度 前期 始業式(令和7年4月7日)
 皆さん,おはようございます。
皆さん,おはようございます。
令和7年度の始まりに当たり,お話をします。
皆さん,今日から,それぞれ新2年生,新3年生ですね。
まず,新2年生の皆さん,1年生と2年生の大きな違いって何でしょうね。
そうですね。文系のコースと理系のコースに分かれるということですかね。
日本の多くの普通科の高校においては,私たちの学校と同じように2年生から文系・理系のコースに分かれる学校が一般的です。これは,普通科の高校の卒業生の進路先が大学を中心とする上級の学校であり,その大学等のカリキュラムの在り方,そして何よりも,大学の入試の在り方が,文系学部であれば,国語・地歴公民科などの比重が大きく,理系学部であれば数学・理科等の教科の比重が大きい。(英語については文理共に重視していますが・・)このことから,高等学校の教育課程においてもそれにあわせて,文系教科・理系教科をそれぞれに学べるようにしておくという理由からなのです。
文理選択をきっかけに,皆さんも,高校卒業後,大学で自分がどのような研究をやりたいのか,そのために高校で,どのようなことに力を入れていかなければならないのか。また,大学を出た後は,どのような職業・仕事に就職して,その仕事を進めるために,これまで学んだことをどのように生かしていくのかとか,を考えただろうと思います。小学校の時に漢字の書き取りや,かけ算九九を覚えているときに,これが将来のこんな仕事につながるだろうと思って勉強はしていなかったと思いますが,おそらくこれからの学びというものは自分の将来に直接つながっていく学びになるのだろうと思います。高校2年生からは「今,学んでいることと自分の将来との繋がり」を意識する時期に入ったわけです。これって,長い人生を通してみても結構重要な時期に入ってきたのだと思うのです。
理科や地歴公民科の教科などいろいろな教科が本格的に入ってくることで,高校1年生の時にはちょっと力を発揮できなかった人が,これをきっかけにして,いい方向に変わっていく事例もこれまでに見てきました。高校生が大きく変わるのは2年生の時期だとも言われています。この4月・5月の最初の時期が大切だと思います。もう1回鶴丸高校に入学したつもりで,新鮮な気持ちで授業に臨んでほしいと思います。
3年生は4月~6月の時期が覚悟を決める時期かもしれませんね。昨年度末に進路指導の先生が言っていましたが,夏にはもう志望大学別の大の模擬試験を受ける時期になるわけですから,進路先を検討する時期としては,この春が最後の機会かもしれませんね。
もう既に,私は,この道を行くと考えている人は,もうそれに向けて頑張ってください。ただ,迷っているという人がいたら,春の教育相談期間に新しい担任の先生方などとよくお話をしてくださいね。
「進路に迷っている」という人は,どんな風に迷っていますか?
もし「自分の今の力じゃ,『この大学に行きたい』と口に出すのが恥ずかしい」と,ちょっと消極的になって「どうしよう?」と悩んでいるのであれば,何も遠慮することはありません。自分が本当に行きたい道を進もうと思ってかまわないんじゃないですか?「より高い道」は「より困難な道」かもしれません。でも,あなた方が決意をもって考えた希望先であれば,「そんな進路希望は無謀なのでは?」なんてことは鶴丸高校の先生方は絶対に言わないと思います。しっかりと,背中を押してくれて,一緒にその道を歩いてくださるはずです。
皆さんの1回きりの自分の人生ですよ? まだ1年間もあるんですよ。皆さんはこれから何者にでもなれるのです。チャレンジできるのは若い人の特権。
よく,受験勉強を行うのに「灰色の受験勉強・・・」とかネガティブな言い方をするんですけど,自分の研究したい領域があって,その一流の研究者のいるところで勉強したい。とか,最新の施設設備が整った環境のいいところで研究したい。とか,日本中から,また世界からやってくる同じ志をもった研究者と机を並べて勉強したい。
こういった夢を叶える努力をすることは,悲壮感をもって「どうしよう~」と悩みながらやる性質のものでなく,基本「ワクワク」してやらなきゃいけない。そして,これは,学級の中とか受ける授業の雰囲気が,大切で,前向きさとか,やる気とかは伝染するものなんです。隣の友達見ていたら,前向きでやる気に満ちている。自分も頑張ろう。そんな雰囲気ができたら,この3年生は一人一人がいい流れの中で勉強ができると思いますけどね。
3年生は今年1年,友達同士で「がんばろうよ」という雰囲気を作ってみてください。
さて,この後は,その雰囲気づくりに欠かせない新しい「学級」の発表ですよね。
新しい学級となって,皆さんの周りに,話したこともない,初めて会うような新しい友達が自分の周りにやってくるかもしれません。ドキドキしますね。人間は個人として存在していても,絶えず他者との関係,人と人との関わりを通して生活していきます。人と人の関係性の中で生きています。
級友,クラスメートというのは,人生のかなり早い時期に出会う,家族以外で結構長い時間を過ごす大切な他者です。今日のクラス替えで成立する新しい環境,そしてその環境をどうしていくかということは,これは,やはり,大切な重要な問題だと思うんですよ。
仲の良かった友人と離れてしまって残念な思いをする人もいるかもしれません。しかし,そういう人は,これは,たくさんの新しい友人ができるチャンス,自分自身の視野をひろげるチャンス,今までになかった刺激を受け,自分の幅を広げ,引き出しを増やすチャンスだと思ってください。
逆に,今回の学級は,良かった。知っている友達が多かったなぁ,と思っている人たち,皆さんの周りを見回してください。寂しそうにしている人がいたら是非,声をかけてあげてください。周りの人たちを思いやる気持ち,気配り,やはり,このようなことは,とても大切です。
自らが学ぶ場所である自分の学級を自らの意識と行動で良いものにしていくこと,特に,周囲との人間関係をよりよい方向に構築していくこと,これは,なにより自分自身が安心して生活を送るために重要なことです。
鶴丸高校では学級のことを「ルーム」と呼びます。いいですよね。安心できる空間という感じがします。社会性を涵養するもっとも大切な単位は学校においては学級の空間です。
それぞれが,一人一人が,素晴らしいルームを作る努力をしてください。これが,鶴丸高校全体を良くするということにもつながるように思います。
皆さんの力で,それぞれの学級を,そして鶴丸高校をよりよい場所にしていてほしいと思います。よろしくお願いします。
では,最後に,もう一つ皆さんにお願いがあります。明日,いよいよ君たちの後輩が入学してきます。新1年生たちは,今,期待が半分,そして不安が半分という感じだと思います。私のお願いは,その新入生をしっかりと育ててほしいということです。
生徒を育てるのは,もちろん私たち教師の仕事でもあるんですが,後輩の育成という面においては,皆さんの力によるところが大きいのです。なぜなら,彼らは,君たちもそうであったように周りのどんな人の言葉より君たち鶴丸高校の先輩の言葉を大切に思うからです。鶴丸高校の先輩の立ち振る舞いに大きな影響を受けるからです。
先輩方が,そして君たちが築いてきたこの鶴丸高校の素晴らしい伝統を受け継いでいく新入生を,温かく迎え入れ,導いてあげてください。そのことは君たちにしかできないことなのです。よろしくお願いします。
令和7年度がいよいよ,はじまります。今年度も良い1年間にしていきましょう。
以上,始業式のお話とさせていただきます。
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード