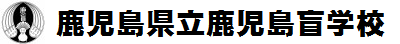公開日 2025年03月21日
[児童生徒,保護者による学校評価] [職員による全体評価の結果] [今年度の重点項目と改善策の実施状況と反省] [次年度の重点項目と改善策]
本年度,実施した学校評価の結果についてお知らせします。
1 児童生徒,保護者による学校評価の結果
(1) 実施月及び対象
令和6年11月 児童生徒及び保護者
(2) 実施方法
保護者及び児童生徒によるアンケート及び自由筆記形式での評価・要望等の記入後,その結果を基に3学期に検討・改善に努めています。
評価4:75%以上 十分達成
評価3:74%~50% おおむね達成
評価2:49%~25% やや不十分
評価1:24%以下 不十分
(3) 保護者 評価結果
| 保護者 評価項目 | 評価平均 | |
| 1 | 学校は,学校目標や取組,行事などについて,学校便り,週報,ホームページ等で分かりやすく伝えている。 | 3.8 |
| 2 | 学校は,特色ある教育活動(学校行事・学部行事等)を行っている。 | 3.8 |
| 3 | 学校は,教室や掲示板等の設営・展示等が工夫され,施設・設備を活用した教育活動を行っている。 | 3.8 |
| 4 | 学校は,児童生徒の健康安全や事故防止等に十分配慮し,感染症に関する情報提供や対策等を行い,安心して生活できるようにしている。 | 3.7 |
| 5 | 学校は,地域や家庭に開かれた学校づくり(交流及び共同学習,PTA活動等)を積極的に進めている。 | 3.7 |
| 6 | 学校は,児童生徒に学力や生活する力の基礎を身に付けるため,きめ細やかな指導やわかりやすい授業をしている。 | 3.7 |
| 7 | 学校は,給食指導や給食献立表・MOGU MOGU通信の発行を通して,食の指導に関する情報を発信している。 | 3.9 |
| 8 | 教師は,協力し合って児童生徒の教育活動を行っている。 | 3.7 |
| 9 | 教師は,個別の教育支援計画や個別の指導計画について,分かりやすく説明している。 | 3.8 |
|
10 |
教師は,児童生徒のことで,保護者の悩みや相談したことについて,適切に対応している。 | 3.7 |
| 11 | 教師は,将来の進路などについて,丁寧に指導している。 | 3.3 |
| 12 | 児童生徒は,学校に行くことを楽しみにしている。 | 3.6 |
| 13 | 児童生徒は,人や生き物などに対して,思いやりのある心が育っている。 | 3.7 |
| 14 | 児童生徒心得は,児童生徒の実態に合っている。 | 3.6 |
(4) 寄宿舎保護者 評価結果
| 寄宿舎保護者 評価項目 | 評価平均 | |
| 1 | 寄宿舎は,寄宿舎生が親睦を深められるような行事(歓迎会や卒業を祝う会,季節の行事等)を行っている。 | 3.8 |
| 2 | 寄宿舎は,学習環境や生活環境が整っている。 | 3.8 |
| 3 | 寄宿舎は,寄宿舎生の健康状態の把握や安全面に十分配慮し,安心して生活できるようにしている。 | 3.7 |
| 4 | 寄宿舎指導員は,相談したことについて適切に対応している。 | 3.8 |
| 5 | 寄宿舎生は,充実した寄宿舎生活を送っている。 | 3.6 |
(5) 小学部児童 評価結果
| 児童用 評価項目 | 評価平均 | |
| 1 | 学校は,学校目標やその取組,行事などについて,全校集会や学部集会,学校便り,週報等で分かりやすく伝えている。 | 3.8 |
| 2 | 学校は,特色のある行事 (学校行事や学部行事等)を行っている。 | 4.0 |
| 3 | 学校は,学習に必要な物や施設・設備がそろっている。 | 4.0 |
| 4 | 学校は,みなさんの健康や事故防止・安全に気を配り,感染症に関する情報提供や対策等を行い,安心して生活できるようにしている。 | 3.7 |
| 5 |
学校は,地域や家庭に開かれた学校づくり(交流及び共同学習,PTA活動等)を積極的に進めている。 |
3.7 |
| 6 | 学校は,みなさんに生活に必要な学力を付けるための指導やわかりやすい授業をしている。 | 3.5 |
| 7 | 学校は,給食指導や給食献立表・MOGU MOGU通信の発行を通して,食の指導に関する情報を発信している。 | 4.0 |
| 8 | 先生たちは,協力し合ってみなさんの教育活動を行っている。 | 4.0 |
| 9 | 先生たちは,みなさん一人一人に応じた指導をしている。 | 4.0 |
| 10 | 先生たちは,みなさんの話や相談をよく聞いている。 | 4.0 |
| 11 | 先生たちは,みなさんの将来の進路などについて,分かりやすく,丁寧に指導している。 | 4.0 |
| 12 | 私たちは,充実した学校生活を送っている。 | 3.7 |
(6) 中学部生徒 評価結果
| 生徒用 評価項目 | 評価平均 | |
| 1 | 学校は,学校目標やその取組,行事などについて,全校集会や学部集会,学校便り,週報等で分かりやすく伝えている。 | 3.4 |
| 2 | 学校は,特色のある行事 (学校行事や学部行事等)を行っている。 | 3.6 |
| 3 | 学校は,学習に必要な物や施設・設備がそろっている。 | 4.0 |
| 4 | 学校は,みなさんの健康や事故防止・安全に気を配り,感染症に関する情報提供や対策等を行い,安心して生活できるようにしている。 | 4.0 |
| 5 |
学校は,地域や家庭に開かれた学校づくり(交流及び共同学習,PTA活動等)を積極的に進めている。 |
3.8 |
| 6 | 学校は,みなさんに生活に必要な学力を付けるための指導やわかりやすい授業をしている。 | 4.0 |
| 7 | 学校は,給食指導や給食献立表・MOGU MOGU通信の発行を通して,食の指導に関する情報を発信している。 | 4.0 |
| 8 | 先生たちは,協力し合ってみなさんの教育活動を行っている。 | 4.0 |
| 9 | 先生たちは,みなさん一人一人に応じた指導をしている。 | 3.6 |
| 10 | 先生たちは,みなさんの話や相談をよく聞いている。 | 4.0 |
| 11 | 先生たちは,みなさんの将来の進路などについて,分かりやすく,丁寧に指導している。 | 3.6 |
| 12 | 私たちは,充実した学校生活を送っている。 | 4.0 |
(7) 高等部普通科生徒 評価結果
| 生徒用 評価項目 | 評価平均 | |
| 1 | 学校は,学校目標やその取組,行事などについて,全校集会や学部集会,学校便り,週報等で分かりやすく伝えている。 | 3.0 |
| 2 | 学校は,特色のある行事 (学校行事や学部行事等)を行っている。 | 3.0 |
| 3 | 学校は,学習に必要な物や施設・設備がそろっている。 | 3.5 |
| 4 | 学校は,みなさんの健康や事故防止・安全に気を配り,感染症に関する情報提供や対策等を行い,安心して生活できるようにしている。 | 3.5 |
| 5 |
学校は,地域や家庭に開かれた学校づくり(交流及び共同学習,PTA活動等)を積極的に進めている。 |
3.3 |
| 6 | 学校は,みなさんに生活に必要な学力を付けるための指導やわかりやすい授業をしている。 | 3.3 |
| 7 | 学校は,給食指導や給食献立表・MOGU MOGU通信の発行を通して,食の指導に関する情報を発信している。 | 3.5 |
| 8 | 先生たちは,協力し合ってみなさんの教育活動を行っている。 | 3.3 |
| 9 | 先生たちは,みなさん一人一人に応じた指導をしている。 | 3.0 |
| 10 | 先生たちは,みなさんの話や相談をよく聞いている。 | 2.8 |
| 11 | 先生たちは,みなさんの将来の進路などについて,分かりやすく,丁寧に指導している。 | 3.0 |
| 12 | 私たちは,充実した学校生活を送っている。 | 3.3 |
(8) 高等部保健理療科・専攻科 評価結果
| 生徒用 評価項目 | 評価平均 | |
| 1 | 学校は,学校目標やその取組,行事などについて,全校集会や学部集会,学校便り,週報等で分かりやすく伝えている。 | 3.5 |
| 2 | 学校は,特色のある行事 (学校行事や学部行事等)を行っている。 | 3.8 |
| 3 | 学校は,学習に必要な物や施設・設備がそろっている。 | 3.9 |
| 4 | 学校は,みなさんの健康や事故防止・安全に気を配り,感染症に関する情報提供や対策等を行い,安心して生活できるようにしている。 | 3.8 |
| 5 |
学校は,地域や家庭に開かれた学校づくり(交流及び共同学習,PTA活動等)を積極的に進めている。 |
3.8 |
| 6 | 学校は,みなさんに生活に必要な学力を付けるための指導やわかりやすい授業をしている。 | 3.6 |
| 7 | 学校は,給食指導や給食献立表・MOGU MOGU通信の発行を通して,食の指導に関する情報を発信している。 | 3.9 |
| 8 | 先生たちは,協力し合ってみなさんの教育活動を行っている。 | 3.5 |
| 9 | 先生たちは,みなさん一人一人に応じた指導をしている。 | 3.8 |
| 10 | 先生たちは,みなさんの話や相談をよく聞いている。 | 3.5 |
| 11 | 先生たちは,みなさんの将来の進路などについて,分かりやすく,丁寧に指導している。 | 3.9 |
| 12 | 私たちは,充実した学校生活を送っている。 | 3.6 |
(9) 寄宿舎児童生徒 評価結果
| 寄宿舎児童生徒用 評価項目 | 評価平均 | |
| 1 | 寄宿舎は,みなさんが友情を深めるような行事(歓迎会や卒業を祝う会,季節の行事など)を行っている。 | 3.8 |
| 2 | 寄宿舎は,学習環境や生活環境が整っている。 | 3.8 |
| 3 | 寄宿舎は,みなさんの健康や安全に気を配り,安心して生活できるようにしている。 | 3.7 |
| 4 | 寄宿舎の先生たちは,みなさんの話や相談をよく聞いている。 | 3.8 |
| 5 | 私は,充実した寄宿舎生活を送っている。 | 3.6 |
[児童生徒,保護者による学校評価] [職員による全体評価の結果] [今年度の重点項目と改善策の実施状況と反省] [次年度の重点項目と改善策]
2 職員による全体評価の結果について
実施月及び対象
令和6年11月 職員
実施方法
全職員によるアンケート及び自由筆記形式での評価・要望等の記入後,その結果を基に3学期に検討改善に努めています。
評価4:75%以上 十分達成
評価3:74%~50% おおむね達成
評価2:49%~25% やや不十分
評価1:24%以下 不十分
職員 評価結果
| 内容 | 評価平均 | |
| 1 | 学校経営についての項目 | 3.4 |
| 2 | 教務についての項目 | 3.6 |
| 3 | 生徒指導についての項目 | 3.6 |
| 4 | 進路指導についての項目 | 3.6 |
| 5 | 保健についての項目 | 3.4 |
| 6 | 自立活動についての項目 | 3.6 |
| 7 | 教育支援についての項目 | 3.5 |
| 8 | 寮務についての項目 | 3.6 |
| 9 | 事務についての項目 | 3.8 |
[児童生徒,保護者による学校評価] [職員による全体評価の結果] [今年度の重点項目と改善策の実施状況と反省] [次年度の重点項目と改善策]
3 令和6年度の重点項目と改善策の実施状況と反省
1 分かる授業づくりや体験学習・行事の充実
・ 児童生徒の成長や活躍,視覚障害教育の良さを共有できる①実習②行事③交流
① 実習
○ 中学部では,3年生がファッションセンターしまむら,たわわタウンで3日間職場体験を,2年生がマクドナルド中山店で職場見学を行った。また,1年生は,本校専攻科の授業見学を行った。
○ 高等部普通科では,3年生が南日本銀行で事務を,生活介護事業所アオラでは介護補助の職場等実習を3日間おこなった。また,1年生は,生活介護事業所喜々とアオラで1週間ずつ産業現場等における職場実習を行った。
○ 高等部専攻科では,鹿児島県庁での実習(全学年),城山観光株式会社,鹿児島銀行(理療科2年,3年)でヘルスキーパーの実習を行った。
② 行事
○ 今年度は,文化祭を行い,各学部,工夫を凝らした発表をすることができた。
③ 交流
○ 小学部では,昨年度開始した重複障害学級の鹿児島南特別支援学校との交流及び共同学習を,初めて子どもたちを本校に招いて実施した。学部全体で取り組む,鹿児島市教委指定の小学校との交流及び共同学習も継続できている。(他,オンラインのことは下記のとおり)
○ 中学部では,居住地校交流や錫山中学校との交流及び共同学習を行った。
○ 高等部普通科では,鹿児島南高等学校との交流に加え,授業体験として3年生は,3時間目から昼休み,清掃の時間,5時間目まで一緒に活動する交流を行った。また,1年生は鹿児島南特別支援学校で音楽の交流学習を行った。
・ PTA合同レクリエーションやPTA親子研修会などPTA活動の充実
○ 今年度もPTA合同レクを行い,他学部の保護者や児童・生徒と交流することができた。また,PTA親子研修会では,保護者の希望をもとに点字の仕組みや読み方の研修を本校教師が講師となり実施した。保護者の点字体験では,児童・生徒が問題を出し合い,補助を行い,交流しながらの研修を行うことができ,参加した保護者から,とても楽しかったし初めて知ることがあったと,好評だった。
・ 他県の盲学校や県内外の学校との「交流及び共同学習」におけるICT活用
○ 小学部はオンラインで他県の視覚支援学校及び盲学校や鹿児島特別支援学校との交流及び共同学習を行った。在籍が一人しかいない学級が多いので,話し合いや調べ学習の発表,意見や感想を述べ合う場と,互いの成長を喜び合える場にもなっている。
○ 中学部は,オンラインで旭川盲学校と交流及び共同学習を行った。
・ 相互授業参観の活用と充実
○ 相互授業参観前に,各主事より時間割を提示していただき,互いに授業を参観できる環境を整えたが,学部によっては時間調整ができずに,参観回数が少なかった学部もあった。
○ 高等部では,指導略案を作成し,相互参観を行った。
・ 進路相談や教育相談のニーズ把握とケースに応じた,寄宿舎,他学部乗り入れ
○ 盲学校での進路指導について,乳幼児教育相談の保護者や教職員,中学部保護者に話す機会を設定してもらった。
・ 心に届く言葉掛けや関わり(前向きな評価と真摯な相談)
○ 心に届く言葉掛けや関わりを行っているのだが,まだまだ真摯な取組が必要である。
2 視覚支援教育に関する情報共有・情報発信
・ 本校教育や”あはき”の魅力の発信と啓発(学校安心安全メール・各種たより・眼科医・報道機関・ホームページ等)
○ 北薩地区と志布志地区の民生委員・児童委員に対して啓発の一環として,専攻科と学校の紹介を行った。また,鹿児島県高等学校養護教諭研究会に参加し,視覚障害者についての講話を行った。
○ 北薩,志布志地区の眼科医を訪問し,パンフレットを置いてもらった。
○ 24時間テレビのイベントに参加し,あん摩マッサージブースで啓発活動を行った。盲学校を知ってもらう機会となった。
・ 白杖歩行や点字の指導,弱視レンズや拡大読書器等を活用する学習の充実
○ 自立活動部を中心にミニ講座を行い,職員の研修を行うことで,生徒への指導の充実につなげた。
○ 福祉機器展示会にて最近の情報収集ができた。
・ 進路に関する分かりやすい情報提供(含:進路ガイダンス・進路先訪問研修)
○ 進路指導についての全体研修を行ったり,保護者への説明などを行ったりした。
○ 卒業生の進路先を訪問し,仕事の様子や生活について話を聞くことができた。
・ 関係学校・機関等との連携等,本校内外の視覚障害のある方を”孤立させない”働き掛け(視覚障害教育のセンター的機能の発揮)
○ 巡回相談を定期的に行い,学習支援や就学相談,進路相談の対応を行った。巡回相談先では,対象児の読み速度の検査や,保護者との相談,担任や管理職との研修等の中で,数多くの質問や悩みを寄せられ,県唯一の視覚支援特別支援学校のセンター的役割の大切さを痛感した。専門性の維持・継承・向上が課題である。
○ 「孤立させない働き掛け」について,本校から地域の学校へ転校した弱視児についても毎月の定期来校相談で,点字を中心とした学習や相談を継続し,保護者同士の絆もつながっており,盲学校からの情報や支援がありがたいと,相手校含めて喜ばれている。
・ 職員同士,職員と保護者,保護者同士,関係機関をつなぐ取組(学びの機会も確保)
○ 職員対象の研修が,夏季休業中に組まれ学びの機会を確保することができた。
○ 関係機関への訪問,連携をすることでヘルスキーパーの啓発を進めることができた。
・ 児童生徒の眼疾患や発達の段階などに応じたICTの導入や情報提供
○ 学校見学会に合わせて,最新の視覚支援機器の展示会を行い,多くの方に見てもらうことができた。
・ 学校見学会や研修会等への関係者招へい,保護者への参観呼び掛け
○ 学校見学会に眼鏡のヨネザワさんにお越しいただき,視覚支援機器の展示と解説をしていただいた。昨年度初開催だったが,今年はPTA総会でニーズを把握し,一日中の開催に変更したところ,午後に参加し最新の視覚支援機器を体験できた保護者や本校児童生徒,教職員も多く,アンケート結果からもとても貴重な機会で,初めて知ったものもあったし,視覚障害教育の深さが分かったなどと,好評な感想が多く寄せられた。
○ 職員研修では,外部講師を招へいし,実りある研修を行うことができた。
[児童生徒,保護者による学校評価] [職員による全体評価の結果] [今年度の重点項目と改善策の実施状況と反省][次年度の重点項目と改善策]
4 次年度の重点項目と改善策
本年度の保護者・児童生徒の学校評価及び職員による全体評価の結果から考察し,次年度,継続したスローガンのもと,以下を次年度の重点項目としたいと考えます。
|
スローガン「言葉をかけあい※ つながる 盲学校」 ⑴ 「学校が楽しい」と感じる学校作り ⑵ 児童・生徒の心に届く相談体制の充実 ⑶ 視覚支援教育に関する情報発信と専門性の継承・維持・向上 ※ 「言葉を掛け合い」と「言葉を掛け 会い」両方の意味 |
⑴ 「学校が楽しい」と感じる学校作り
・ 児童・生徒の実態に応じたICT機器の活用や体験活動等を取り入れた多様な学び方ができる授業展開を行う。
・ 児童・生徒が安心して,みんなが考え,支え合い,想像することを通して,それぞれの課題を解決していくことができる学級・学部作りを行う。
・ 県内外の学校との「交流及び共同学習」や「居住地校交流」等を通して,地域や学校との連携を深める。
⑵ 児童・生徒の心に届く相談体制の充実
・ 進路に関する情報提供や自己理解を深める授業等を行い,児童・生徒の意識を高めるとともに一人一人のニーズに応じた個別相談を行う。
・ 施設参観や研修会等のPTA事業を通じて,学校と家庭,保護者間の連携を深め,充実を図る。
・ 外部専門家や支援部,進路部,人権同和係など,相談窓口を複数設定して,児童・生徒と向き合い,信頼関係を構築することで,相談体制の充実を図る。
⑶ 視覚支援教育に関する情報発信と専門性の継承・維持・向上
・ 進路研修会や視覚支援機器の展示会,校外に向けた”あはき”の魅力の発信,啓発を行う。
・ 関係学校・機関等,本校内外の視覚障害のある方を”孤立させない”働きかけを行う。
・ 相互授業参観等を通して,効果的な指導法の共有,支援ツールの活用促進などについて研修を深め,専門的な指導力の向上を目指す。
[児童生徒,保護者による学校評価] [職員による全体評価の結果] [今年度の重点項目と改善策の実施状況と反省][次年度の重点項目と改善策]